コロナ禍で先行き不透明な中、何度か手にしたマーケティングの本があります。
『マーケティング戦略の実際』。
新しい年度が始まるにあたって、改めて読み返しました。
戦略デザイン研究所所長でMCEI(Marketing Communications Executives International)東京支部・大阪支部の創設者、故・水口健次氏の著書。
1983年に1版が出て2007年には3版10刷となっています。ロングセラーです。
本の最後に、実務家、水口マーケティングのキーポイントが7つ挙げられて整理されています。
7番目は、“朝は夜より賢い”。引用します。
「これは、本文に書いていないことです。人間というもの、朝は夜より賢い、と思います。思い悩むことが山ほどありますが、精一杯努力して、疲れたら飲んで寝るー それしかないと思います。朝は夜より賢いのです。明日はまた、新しい知恵と勇気が出てくるはずです」
少し煮詰まったら、いつも思い出し、勇気づけられる言葉。
“水口語録”と呼ばれる数多くの金言を残しておられます。
2008年に逝去されるまで、MCEI大阪支部1月の定例会は水口健次さんの新年の提言をお聞きするのが恒例でした。
その中で、いつも口にされていて、印象に残っているのが次の2つの言葉
「マーケティングは愛だ」
「すべてのコストの負担者はお客様である」
MCEI大阪支部のホームページには「水口創設理事長特設ページ」があります。
そこには、プロフィールや功績の他に、「水口健次著書一覧」、「水口健次年表」、「水口健次戦略コラム」を紹介しています。
例えば、「水口健次戦略コラム」を見ると水口氏は卓越した先見性の持ち主であることが分かります。2008年の時点で、ジェネレーションZを顧客として、同時に、従業員として、受け容れなければならない立場にある、恐ろしい時代、難しい時代と言及されています。
前期3月度定例会でも、水口氏の「知覚されないニーズ=生活者インサイト」がパネルディスカッションのテーマとして取り上げられました。
MCEIの諸先輩方は、よくご存知かと思いますが、是非、下記サイトをご覧いただければ嬉しいです。
また、これを機会に「水口ゼミナールリレーコラム」をスタートしますので、ご期待下さい。
↓以下からリンクしております。
【MCEI大阪支部「水口健次創設理事長ページ」】
【MCEI大阪支部「水口ゼミナールリレーコラム」】
MCEI大阪8月定例会が開催された8月6日は、大阪府からのミナミのお店に対して営業時間短縮、休業要請のあった初日でした。その大変な中、ご登壇いただいたのが千房ホールディングス株式会社 代表取締役社長の中井貫二さん。「経営は終わりのない駅伝」と題してお話いただきました。
千房さんといえば、個人的にはラジオ大阪の番組「鶴瓶・新野のぬかるみの世界」がきっかけで、大学生の頃に初めて行ったのを思い出します。今でも“ぬかる民”の裏メニュー「ぬかるみ焼き」は注文があればどのお店でも食べることが出来るとのことですよ。

1973年創業の千房さん、現在、FCを含めて、千房グループで国内79店舗、海外7店舗を運営されています。6月に虎ノ門ヒルズにオープンした「琥 千房 虎ノ門」は千房グループ最高峰の業態「クラシックス」で、お客様の単価5万円と超高価格にもかかわらず大人気というから驚きです。百貨店やホテルへの出店、機内食の提供など業界初のチャレンジをされています。昔から、従業員の皆さんに常々言ってきているという“やらかす千房”の合言葉が活かされています。「『や』わらかな発想で、『ら』しさを大切にして、『か』んがえたことは、『す』ぐにやる!」を意味しています。千房のオリジナリティの源ですね。
中井社長が掲げられた3つのテーマは、「グローバル視点」、「受け継がれるおもてなし」、「飲食店は共育産業」。「グローバル視点」では、インバウンド、アウトバウンドのシナジー効果やお客様に喜んでいただくための環境整備に注力。日本人、外国人も分け隔ての無いおもてなしで期待に応えたい“大阪らしさ”を伝えたいということで、「まいど」、「おおきに」といつも通りの接客をされています。ハラル対応、グルテンフリー対応もすでに導入されています。先日、私もグルテンフリーのお好み焼をいただいてみました。ふわふわとしていてこれが美味しい、当たり前のように美味しいのがいいですね。
千房さんでは「おもてなし」のマニュアルがないとのこと。“見返りを期待しない、お客様の想定を大幅に上回るサービスを提供する”、この「大幅に上回る」というのがポイントです。
「飲食店は共育産業」という点では社会貢献として「出所者雇用」を熱心に続けているのは有名です。社員教育は、外部ではなく社内のスタッフで実施しています。“共育”で“人財育成”。
「ピンチはチャンス、チャンスはチェンジ、チェンジはチャレンジ」。
コロナ禍の影響で千房グループさんも大きな打撃を受けています。先ずは、売上・利益効率・体制等、短期目標達成のために、”Reborn Project”としてスクラップ&ビルトや体制強化などに着手。同時に、中長期目標を掲げ、外食企業の可能性の追求にとどまらず、既存資産を活用した食をコアにしたコングロマリットの構築に向けて始動されています。
“「従業員の幸福」がなければ「お客様のご満足」はない、「お客様のご満足」がなければ「会社の発展」はない”、という三位一体経営で、「世界一従業員が幸せな会社にしたい」。
子どもの時から「従業員のおかげで食べていけてるんやぞ」と言われて育った中井社長の目指す所です。
お話の中で、随所に、現会長であるお父様の創業者理念を大切にされてることが出てきました。事業を継承していく面と革新していく面、この二つを兼ね備えているのが中井社長ですね。
講演の題目として挙げられた「経営は終わりのない駅伝」。マラソンは一人で走るためその距離も時間も限られていますが、駅伝はタスキをつなぎます。中井社長は、創業者のお父様、急逝されたお兄様を経て、“千房経営”のタスキを受け取られました。経営者の大きな役割として、100年企業に向けて自分のタスキをどうつないでいくかを考えておられることと思います。
6月、新聞に掲載されていた千房さんの広告、強烈な印象が残っています。
「負けへんで 絶対ひっくり返したるっ “美味しい”はコロナにまけへん。」

二〇世紀はテクノロジーの進歩により環境の変化が印象的だ。二一世紀も単線的に続くと思われた。近代以降の人々の考え方では、世界は大体理解できるものだというのが支配的だが、未知のもの・合理的理解の不能な世界がある。その外界としての世界への関心・理解はモノの価値を生み出す原則と深くかかわっていくことになる。
「見えないものに気付く」から「見えないものをカタチにする」「言葉にできないものをカタチにする」など新しい方法が必要だ。自分で見てきて、知ることが大切だ。その場に行って見るということは、やはり大きなことだと思う。仮想のイメージや複製されたもので何かを語ることは危険である。人の噂に左右されない方がいい。そうやたらに信じない、まず疑ってかかるという意識を持つこと、誰か人が何かを言ったらすぐに信じることなく、その現場に行って状況を自分の目でみようということ。この行動が実務の場での気付きにつながる。
何ごともない平和なときだったら、何が大事で何が大事ではないかというモノの価値の段階がある。資本主義社会ですら大抵のものには正札がついていて値段の高いものはいいとか、値段の低いものは良くないとか値段の段階がある。ところが戦争とまではいかないが今回の世界的パンデミックで、身近に死が迫ってくると、そういった段階が崩れる。どちらでもよくなるのである。要するに正札が取れてしまう。これは一種の価値の転換だ。見えない価値に気付くということなのだ。
2000年からMCEI大阪支部で理事をひきうけて、ほぼ20年がたった。その間の多くの気付きは私の方法論を成長させてくれた。
最後に、 「神々は異邦人のふりをして諸国を放浪する。」 ―ホメロスー
私もこのひと区切りで、旅をしてみることにする。
2020年5月19日
橋詰 仁
はじめに
暖冬が続く中、2月定例会は4月初旬並みの暖かさで迎えた。2月MCEI大阪定例会はgraf服部滋樹氏の講演である。2010年12月以来実に9年振りの登壇である。その時のテーマは「grafの考える“暮らし”のデザイン」であった。今回のテーマは「リサーチライティングーデザインの可能性と使い方」である。デザインをどのように日々の暮らしの中で活用していくのかという方法論である。服部氏がgrafを立ち上げてから22年にお歳月が経った。20世紀が終わろうとする時にgrafは誕生したのだ。服部さんはデザイン教育にも携わってきた。

最初は京都精華大学の建築領域でデザインフィロソフィを教えていた。建築形態を描く前に建築を立ち上げるしくみやコンセプトが環境にどう関わっていくのかと言うことである。現在は京都造形芸術大学で教鞭をとっていて、今年で11年目を向かえている。情報デザインを基本として、21世紀となり時代が大きく変化する中で、インフォメーションからコミュニケーションへと情報デザインの中心テーマを移して「誰のために何をどの様にコミュニケーションするのか」がデザイン教育の中心テーマとなっている様だ。本日の講演の冒頭に、服部さんは身振りに言葉を添えて「林檎」を表現して見せた。そして子供の頃風邪にかかったとき、母親が林檎をすりつぶして食べさせてくれた時に話を添えて見せた。会場のオーディエンスの多くがその記憶を共有し心開かれたのではないかと感じた。服部さんの「物語」が始まった。

graf の起源から
ここでgrafのことに触れる。服部さんが大学を卒業したのは1993年、ちょうど2年前にバブルは崩壊し「就職氷河期」と呼ばれる時代を迎えていた。このバブル崩壊をきっかけとして、これまでの社会構造に疑問を持ったことがgrafの起源となった。20世紀特に第二次世界大戦後の日本のデザインは焼け野原から始まり、デザイン=機能性のもとに生活に便利なモノを大量に生産することに突き進む。一例を上げれば本田のスーパーカブなどは戦後わずか10年で量産にこぎつけている。1960年より高度経済成長期を向かえデザイン=嗜好性のもとに様々な流行を生み出し、デザインは様々な変化を見せた。機能は同じでも表層のデザインを変えることで消費も細分化されていった。1970年代から80年代は、デザイン=豊かさでありデザイン=経済であったのだ。結果大量生産・大量消費の下にモノつくりが進められバブルが崩壊したのだ。戦後からバブル崩壊まで日本の社会は縦型であったと服部さんは感じたのだ。「縦型って、まずトップにメーカーがいて、その下に生産者がいてユーザーがいて、その中で強いのはいつもメーカー側。泣かされるのは結局、生産者なんですよね。そういう構造的な問題を考えたときに、デザインや企画をする人達も生産者もユーザーも、みんな上下のない横型のものづくりができひんかなって思ったんですよ。」grafをつくろうと思った最初のきっかけを服部さんは語る。1970年以降、ライフスタイルがとなえられ人々を様々なライフスタイルに嵌める広告が溢れ、社会はモノとコトに覆われる。生産の効率上の問題で、あらゆる分野が細分化していき、縦型の生産構造になっていったのが20世紀であった。しかし改めて考えてみれば、もともとは経済も文化も食も、全て同列に生活の中に格納されているもので、この意識をもとに考えると、自分たちがすべきは全ての基盤である「生活」と向き合い、横の繋がりを大切にすることではないかという考え方に辿りついたのだ。バブルをきっかけにして、社会ではなく生活に注目できたことは大きかったと語る。生活を基本にした上で、自分たちでものづくりをして生きていく仕組みとは何か。最初に集まった6人のメンバーは議論を重ねて、グラフの基本理念である「暮らしのための構造」という考え方が生まれた。カテゴリーにとらわれず、様々な視点を持って「生活」を考える。このグラフ独自のものづくりの発想は、立ち上げ当初に集まった、全く個性の違う異業種のメンバーが集まったから生まれたのだgrafは大阪を拠点に「暮らし」にまつわるあらゆるものをデザインしているクリエイティブ集団である。このグラフのスターティングメンバーはバラエティ豊かである。グラフィックとプロダクトのデザイナー、映像作家の他に、家具職人や大工、シェフまでいる。服部さん自身大学では彫刻を学んだ。その活動はデザイン制作から家具作り、カフェの運営、国際的アーティストとのコラボレーション、企業のブランディング、マーケット形式のコミュニティプロジェクトなど多岐に渡っている。異業種が集まりジャンルにとらわれず、独自の視点で活動している。様々なジャンルを飛び越え縦横無尽に活躍する現在のgraf。学生時代に出会った仲間に服部さんは最初に「オレ、”少年探偵団“みたいなチームを作りたいねん。」と語りかけた。

21世紀デザインの方法論
ここで服部さんが上げるデザインの方法論について述べてみる。
Research Writing
マーケティングはニーズに応えて利益を上げること。企業が売りたいモノを売る(プロダクトアウト)から消費者が欲しいモノを売る(マーケットイン)の発想があり、このように目的を持ったリサーチが従来の方法であったが、服部さんは生産者との出合いからモノを組み立てるためにリサーチを位置付ける。このフィールドワークでの出合いからモノを組み立てていく。服部さんは事例として農業を上げる、日本の農業も代替わりして親の代では農協へ納めていた生産物を直接ユーザーへ届けるためのマーケットでの接点を求めている。2010年ある雑誌社の企画で畑づくりを始めたグラフ、不慣れな農作業で悪戦苦闘する中、周囲の農家が手助けしてくれた。彼らと親しくなる中で農家が抱える生産者としての悩みを知ることになる。「卸し先に出荷するだけの生産工場として野菜をつくるのではなく、顔の見える人達のためにものづくりをしたい。」この農家の人達の悩みを受けて始まったのが、マルシェ形式のコミュニティプロジェクト「ファンタスティックマーケット」だ。「出会い、繋がる、広がる」をテーマにしたマーケットである。デザイン事業も農業も広い意味ではものづくりで繋がっているのだ。
モノ本来の価値はネットの波及で大きく変わった。モノを目利きする能力が減衰していく中で、直接知覚できるリサーチが重要となっている。物語を服部さんは物(モノ)と語(カタリ)に分解する。かつて物が語る時代があったように楽しく語ることが大事であるという。使い方より作られ方を語ることがブランディングの要点であるという。レタスの包装もサラダの写真ではなくて生産者の顔を載せるようになっている。
Wisdom Report
暮らしの中の知恵をリサーチして、そこから得られた知恵でデザインを発送すること。服部さんが教育の現場から話された台湾の学生が暮らしの中から取り上げ発想した幾つかのデザイン事例は刺激的で暮らしを豊かにするヒントが豊富にある。蟻がテーブルに上がってこないように脚部の床との接地面に取り付けられた水を張った陶器のソーサ、皿とワイングラスとカップを組み合わせたケーキの展示台は幾つかのモノを用途にこだわらず斬新に組み合わせたデザイン、充電時に床に置かれた携帯電話を床から浮かせて位置付けるための笊、幾つかの用途やモノが組み合わされ、利害関係を超えた3者以上の関係性の提案だともいえる。21世紀のデザインは二つ以上のモノや価値を掛け合わせるクロスイノベーションを試みて、これが新カテゴリーを生むための方法論となる。

Verb Report
動詞の連鎖で暮らしが成り立っている。経験を重ねて無意識の中に暮らしの動作が成り立っている。服部さんはアフォーダンス、アフォードを操作して暮らしに役立てていくシグニファィアとい概念をあげる。
アフォーダンスとは、動物(有機体)に対する「刺激」という従来の知覚心理学の概念とは異なり、環境に実在する動物(有機体)がその生活する環境を探索することによって獲得することができる意味・価値であると定義される。この概念の起源はゲシュタルト心理学の要求特性と誘発性の概念にあると、この言葉を造語したアメリカの知覚心理学者ジェームズ・J・ギブソンは述べている。「与える、提供する」という意味の英語affordから造られた。デザインにおけるアフォーダンスは、1988年ドナルド・ノーマンがデザインの認知心理学的研究の中で、モノに備わったヒトが知覚できる「行為の可能性」という意味でアフォーダンスを用いている。この文脈での語義が、ユーザーインターフェースやデザインの領域で使われるようになった。アフォーダンスはモノをどう取り扱ったらよいかについての強い手掛かりを示してくれる。たとえばドアノブが無く平らな金属片が付いたドアは、その金属片を押せばよいことを示し、逆に引手の付いたタンスは引けばよいことを示している。これらは体験に基づいて説明無しで取り扱うことができる。しかし本来の意味でのアフォーダンスとは「動物と物の間に存在する行為についての関係性そのもの」の事である。近年デザインの領域で「人と物との関係性をユーザーに伝達すること」「人をある行為に誘導するためのヒントを示す事」といった意味に誤って使われていた。これを修正するためにシグニファイア(sigunifier)という言葉がある。これは対象物と人間との間のインタラクションの可能性を示唆する手掛かりのことで、デザイン用語としてノーマンによって提唱されたものである。

結びとして
21世紀は価値観が大きく変化している。モノが成り立つ本質や作り方に興味を持つ人が増えてきた。コミュニティでモノや仕組みを作り上げる人々も増えている。しっかりと丁寧に淀みなく作り続づけられる長続きするPROGRAMが必要である。実験的行為であるPROJECT>PROGPAM>MOVEMENT>CULRTUREのサイクルである。ユーザーとかコミュニティにアクセスしプロジェクトよりプログラムを生みムーブメントに高めカルチャーとして定着させる。これが服部さんの方法論である。
ソーシャルデザインからシンバイオテックリレーションへ、腸内環境のアナロジーともいえる共生関係をどの様に生み出すかが重要となる。「僕ね、どうしてデザイナーやってはるんですかって聞かれたら、いっつもこう答えるんですよ。おじいちゃんになった時に、世界中にたくさん仲間がいたら良いと思うから。」服部さんのこの言葉こそが、幅広い分野を横断するgrafの活動を象徴的に表した言葉である。

80年代頃まで日本のデザインは、個的な問題や表層的な形態(かたち)などの限定された範囲でとらえられ、社会や歴史との深い関わりや有用行為としての見方は希薄であった。しかし90年代以降から現在に至って、デザインは社会や生活に重要な役割と関わりを持つようになっている。また「時代を表徴するデザイン」をめぐっては様々な認識闘争が展開されてきた。この変革の時代を経て現在の状況にあるわけだ。この変化の根底にあるのは、社会・経済・政治・地球環境の構造的危機などの20世紀を支配してきた自然科学や近代主義への警鐘や、人芸性や精神性に基づくコミュニケーションと物質との関係、共同体システムや生活の変化が実は芸術や表現活動と本質の部分で密接に関連していたコトへの“気づき”として表出してきているのだ。今後さらに進展し続ける情報技術が生み出す大海原の中で、デザインの実用体系が大きく組み替えられ、それが生成される時に多くの矛盾を露呈している。それらはまさに個としての恣意性を超えたシステムの問題であり、デザイン行為という専門的技術体系を超えた情報性・認識性の問題であったりする。結論的に述べれば、いまデザインに必要とされるのは「方法」と「認識」である。現在はどこまでがデザインの領域と呼べるのか規定することは難しいが、少なくともデジタルに細分化された思考体系を、デザイナーが持つべき「認識」によって、またデザイン技術の総合性を活かすことによって、文化的手法を結び合わせてその応用によって「関係の時代」を築いていくことが重要となっている。それは人間や民族が本来持っている精神的営み、物語性などの理解への回路と応用に関与する「意匠」という意味で。
はじめに、本郷氏のことから
暖冬の2020年、年頭の定例会はMBSの本郷さんの話から始まる。
本郷義浩氏は1964年京都生まれである。1988年に毎日放送に入社し、一貫して制作局で番組の制作に関わってきた。チーフディレクターを務めた「あまからアベニュー」から引き継がれた「水野真紀の魔法のレストラン」で2001年からプロデユーサーを務め、10%以上の視聴率をとる人気番組となっている。2016年からは京都に関わる番組「京都知新」、「美の京都遺産」、「音舞台」シリーズ、「真実の料理人」などの番組を手掛けて京都のアート系と食関係の職人・アーティストを紹介している。

ネットの存在が大きくなるにつれて、ネットの広告費が右肩上がりに増え続け、テレビの広告費が著しく減少するという傾向がしばらく続き、今は年間1兆7000億円ほどで下げ止まり均衡状態を保っているが、ネットの広告費は現在1兆円超の規模まで膨れ上がり、テレビの広告費に次ぐ規模になっている。「テレビ事業は広告だけではだめ。」MBSメディアホールディングスではこの危機感の中で社員600人に向けて「新規ビジネスコンテスト」を実施した。本郷氏は220件の応募を勝ち抜き、現在は番組制作を続けながら2019年9月よりMBSホールディングスの完全子会社であるMBSイノベーションドライブの中で、新たな「食」に関する事業をプロデュースする株式会TOROMI PRODUCEを立ち上げて事業展開を始めている。本郷氏は代表取締役として就任している。本郷氏は海外でのテレビ賞受賞も50を超え、「麻婆豆腐研究家」を自称し、年間120食以上食するほど偏愛している。
本郷氏は同社が目指すことは、飲食店・商業施設・ホテルなどの「レストランプロデュース」、食フェスやパーティ、セミナー企画等を手掛ける「イベントプロデュース」、TV番組・Webサイトなど「映像コンテンツ制作」食品・調味料やグッズの企画など「商品開発プロデュース」を四つのメイン事業とし、それぞれのシナジー効果によって価値あるサービスを提供することだと述べる。また同社が求める人材については、「自律して仕事に取組み続けられる事、自分なりの世界観を大切にする人材が必要。今まで学んだ経験、様々な芸術や映画などの作品に触れる事で醸成させた自分なりの世界観、世の中に新しい、面白い価値観を提供していきたい意欲などは全てが魅力的な人材の要素と言える。そして何よりも大事なのは「食」への飽くなき探求心。私たちが関わることで日本中の食文化をワンランク上に誘導することが同社の使命である。」と語る。

毎日放送について
株式会社毎日放送、略称MBSは、近畿広域圏を放送対象とする特定地上基幹放送事業者である。大阪では唯一の同一法人によるAMラジオ放送とテレビジョン放送の兼営局で、ラジオはJRNおよびNRNとのクロスネット局で、テレビ放送はJNN系列の準キー局である。
設立は第二次世界大戦終戦の年1947年(昭和22年)、GHQが「放送基本法」と「伝播三法」の立法措置を指令し、1950年(昭和25年)に施行された。これ契機に「民間放送」設立が日本各地で相次ぎ、民間放送会社16社に予備免許が下りた。その中の一つが新日本放送株式会社で、関西政財界の支援の下、毎日新聞社と京阪神急行電鉄(現:阪急阪神ホールディングス)と日本電気(NEC)を中心に設立された。創立の中心となったのは、毎日新聞社を依願退職した高橋信三であった。高橋は民間放送の将来性と必要性を説き、毎日新聞社時代に培った人脈をフルに活用して出資者や番組のスポンサーを募った。

設立途中で出遅れた朝日新聞社の机上案に過ぎなかった朝日放送との合併工作を頑として撥ね付け、公聴会の激しいやりとりの末、漸く新日本放送の開局に漕ぎつけた。毎日放送の前進である新日本放送は1956年12月に朝日放送・朝日新聞社・毎日新聞社と合併して大阪テレビ放送株式会社(OTB)を設立してテレビ放送に参入した。その後大阪ではもう一つテレビチャンネルが割り当てられ、ともに独自のテレビ局を持ちたかった朝日放送と新日本放送は、別々に免許を申請し、朝日放送は大阪テレビ放送と合併し、新日本放送は1958年6月毎日放送に改称した上で、大阪テレビ放送から資本と役員を引き揚げ、1959年3月に独自で準教育テレビ局として開局した。開局当初のテレビスタジオは、堂島の毎日大阪会館南館12階にあった。キー局は紆余曲折の末、日本教育テレビとなり、当時のNET系の純粋なフルネットはMBSだけであり、営業面や報道面で様々なハンディを背負いながらの発足であった。スタジオも小さく、使い勝手も悪かった。しかしMBSはこうしたスタジオ事情を逆手に取り、難波南会館からの「番頭はんと丁稚どん」や梅田花月劇場からの吉本新喜劇中継などの外部公開収録番組が生み出された。

テレビとその歴史
テレビ、テレビジョンはフランス語televisionテレビシオンに由来し「TV」と略されることが多い。teleはギリシア語の「遠く離れた」、visionはラテン語で「視界」という意味である。テレビジョンは放送あるいは通信や遠隔監視に使用される遠方へ映像を送る技術で、テレビ放送は主として電波を使って不特定多数のために放送する仕組みで、動画に加えて音声や付加情報を送ることができる。電波を使わずに有線で送出するケーブルテレビ(CATV)もある。このテレビジョン放送で送られるコンテンツが番組(プログラム)である。日本の電波法での「テレビジョン」の定義は「電波を利用して、静止し、または移動する事物の瞬間的映像を送り、又は受けるための通信設備」となり、放送法ではテレビジョン放送は「静止し、又は移動する事物の瞬間的映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送又は信号を併せ送るものを含む。」と定義している。中国では電信と電話を繋げて「電視」と呼ばれている。
「テレビジョン」の歴史は19世紀に始まる。1873年イギリスで明暗を電気の強弱に変えて遠方に伝えるテレビジョンの開発が始まる。1884年ドイツのポール・ニコプーが直列式の機械走査を実現し「ニコプー円板」を発明した。1897年イタリアのグリエル・マルコーニが電磁波を使って3キロメートル離れた地点間でのモールス信号の無線通信に成功している。1897年ドイツのフェルディナント・ブラウンが受像菅に用いるブラウン管を発明。20世紀に至ると1911年ロシアのボリス・ロージングが世界で初めてブラウン管テレビの送受信実験を公開し、簡単な図形の輪郭の受像に成功するが、実用レベルの受像に至るには映像を電気信号に変換する光電管とそれを増幅する真空管の発達を待たねばならなかった。1925年スコットランドのジョン・ロージ・ベアードが機械式テレビを開発。見分けられる程度の人間の顔の送受信に成功する。1926年に同じくジョン・ロージ・ベアードが王立研究所で動く物体の送受信に成功している。

日本では同年12月に浜松高等工業高校の、高柳健次郎がブラウン管テレビの開発で「イ」の字を表示させた。1927年アメリカのフィロ・ファンズワースが電子テレビ撮像機の開発に成功し、撮像・受像の全電子化が達成された。1929年英国放送協会(BBC)がテレビ実験放送を開始。日本では1931年NHK技術研究所でテレビの研究が開始されたが、戦後の1945年から1946年までGHQにより日本のテレビの研究は禁止されていたが同年7月に禁止令が解除され、NHKにより研究が再開された。1952年松下電器産業(現パナソニック)が日本初の民生用テレビを発売した。1953年にシャープが国産第一号テレビTV3-14Tを175,000円で発売。同年、日本放送協会と民放としては初めて日本テレビがテレビ放送を開始した。当時の主な番組は大相撲、プロレス、プロ野球などのスポーツ中継と記録映画であった。白米10㎏が680円、銭湯の入浴料が15円程度であった当時、テレビの受像機の価格は非常に高価で20万円から30万円程度で当然一般の人々にとっては手が届かなかった。多くの大衆は繁華街や主要駅などに設置された街頭テレビや、街の名士などの一部の富裕世帯宅、喫茶店、蕎麦屋などが客寄せに設置したテレビを視ていた。私もテレビが我が家に届いた日のコトを鮮明に記憶している。その頃テレビは特別な「電視装置」だったのだ。1958年12月23日東京タワーからのテレビ放送が開始され、テレビの時代は本郷氏の生まれた60年代に向かって行くことになる。

次に何が起こるかワクワクして視るもの
テレビは見られているのか、いないのか、よく分からなくなってきた。テレビと視聴者の関係が変化したのだ。テレビとは何かという問いは以前からある。1960年代に出版された書籍「お前はただの現在にすぎない。」は当時のテレビ論の基本となっていて、歴史的名著とも言われている。この考え方を最も具体化したのは萩本欽一氏である。2013年2月1日、テレビ放送が始まって60年を迎えたこの日にNHKは記念番組として「テレビのチカラ」を放映した。その番組で萩本氏が最も影響を受けたテレビ番組として挙げたのは「あさま山荘事件」の中継映像であったと語っている。過激派が立てこもる山荘で何が起こるのか、中継の映像はぶっ続けで山荘を写し続ける。「窓ばかリ写すのね」と萩本氏は言っていた。コントの練習をしていたのに戻ってこない二郎さんが、テレビに写る山荘の窓をじっと見ていたのだ。この気づきから生まれたのが「欽ドン!良い子悪い子普通の子」であった。素人や新人ばかりを起用した番組で、出演者が素人なので次にどんな反応を示すのか分からない、だから面白かった。アドリブがエンターテイメント化するという発想の大転換であった。こうして萩本欽一は“視聴率100%男”と呼ばれ、テレビ史上類のないヒットメーカーになっていったのだ。

その後各時代で一世風靡した「元気が出るテレビ」、「オレたちひょうきん族」、「進め電波少年」などは台本無視でドキュメンタリーの様な制作パターンで欽ちゃんの系譜を継いでいると言える。テレビはこの頃までずっと何かが起こりそうで、次に何が画面に出てくるのかワクワクする電視装置だったのだ。テレビ番組の制作側はまちがいなく「何かが起こりそう」を意識していた。クイズをよく出したり、クイズだけではなくテレビはよく“引っ張る”演出をするが、ふと気が付くと視聴者はもう待てなくなっていたのだ。視聴者としての私は、もう引っ張られなくなっていたのだ。少しでも引っ張れば私はスマホに向かってしまうのだ。現在起こっていることは急速に増大するネット環境であり、それに接触する時間なのだ。これは「モバイルシフト」と呼ばれ、メディア接触のスピード感覚が大きく変わり、接触時間の「緩急」の差が大きく開いていく。モバイルシフトが起こると、メディア接触のスピード感覚が大きく変わり、「緩急」の差がものすごく開く。日常的には“ファストな”メディア接触となり、スマートフォン上で次から次にメディアを渡り歩き、どん欲にコンテンツをむさぼる。ある瞬間にスイッチが入ると、急にコンテンツをじっくり視聴して堪能する。その後またスイッチが入るとファストな接触に戻り次々にメディアを渡り歩く。要するに自分でスピード調節して情報環境を最適化したいのだ。ここに「放送」のように定時にその場にいなくてはならないものとの乖離がある。テレビ離れではなく、放送離れなのだ。

結びとして
ネットが人々の生活の隅々にまで浸透した結果、社会の動きとネット上で騒がれていることが一致する状況がかなり一般化している。社会で起きている事象が、ネット上で可視化される時代に入っている。テレビ番組制作の現場も、ネット上の「ネタ」を集めた番組が増加している。「テレビはすでに壮大なネット文化の中の一部として取り込まれてしまったのかもしれない。」慶応大学 夏野剛氏の意見もある。流行やファッションもインスタグラムなど会員制の交流サイト(SNS)から生まれて世界的なトレンドになる事例もある。レストランに行きたいと思えばネットを視れば実際に行った事のある人のリアルな行動に基づいた情報を得ることが可能だ。ネットが普及するまでは、こうした情報はテレビや雑誌が取材して、その情報をテレビ番組や雑誌の中で知るというのがサイクルであった。10年前までは、テレビと雑誌はとかく反目し合うライバルの様に言われてきたが、現在は共存関係になっている部分も多く見られる。2008年頃からフジテレビなど在京のキー局がネット上に番組公式サイトを作るようになった。潮目は明らかに変わったのだ。「モバイル・シフト」が進みテレビとネットが「敵対」から「共存」へ移行する最中に、本郷氏はTOROMI PRODUCEで64本のビジネスモデルを同時に進行させようとしている。その圧倒的な量の質を落とさせないのは、長年テレビの番組制作の現場で培われた「制作力」に在ると感じた。スタッフは5人だけ、人的ネットワークとアウトソーシングを駆動させながら、大風呂敷を拡げて上手くいくものに絞り込む。「やって失敗するほうが、やらないよりいい。とりあえずやってみる。」「映像」で切り取ると、見えないものが見える。ともいう、向かう視点を定める所に気付きが在ると語る。テレビ番組制作一筋の凄みがそこに在る。
はじめに
今回講演をいただく川島康夫さんとの出会いは、女浄瑠璃を後援する「瑠璃の会」会合であった。いろいろ気さくにお話しいただく中で、川島氏が松下電器産業に勤めていて創業者の松下幸之助とも関わりがあったことが分かった。川島氏は「創業者とは何回か話させていただきました。だから物の見方や考え方がよくわかる。貪るように教えを吸収しました。組合活動はいろいろな人がいるからそれは大変です。しかしひ弱な私をよくぞここまで鍛えてくれたと、感謝しています。」と語る。第9回のゼミは川島氏のご案内で門真市西三荘にあるパナソニックミュージアムを訪ねることになった。

松下電器産業からパナソニックへ
1917年(大正6年)松下幸之助は大阪東成郡鶴橋町(現東成区玉津二丁目)の借家で電球ソケットの製造を始める。当時は妻むめのと妻の弟である井植歳男の3人での営業だった。1918年に大阪市北区西野田大開町に移転し松下電気器具製作所を創立した。ここ現パナソニックの原点である。1927年(昭和21年)自転車用角型ランプを販売、この商品からナショナル(National)の商標を使い始める。1931年(昭和6年)ラジオの生産を開始し、1932年に重要部の特許を買収し、同業メーカーに無償で公開し、戦前のエレクトロニクス業界の発展に寄与した。1935年(昭和10年)12月松下電器産業株式会社に改組し、松下電気、松下無線、松下乾電池、松下電熱、松下金属、松下電気直売など9分社を設立した。1937年(昭和12年)「ナショナル」のロゴ書体「ナショ文字」を制定した。1943年(昭和18年9に軍需産業に本格参入、1945年に日本敗戦により、存外資産のほとんどを失い、1946年にはGHQにより制限会社の指定を受けたが、当時の松下航空工業以外の分社を再統合して事業部制にお戻し、洗濯機などの製造を開始した。
松下電器産業からパナソニックへの社名変更は2008年10月1日である。元々「Panasonic」は海外、「松下」もしくは「National」が国内でと使い分けられてきたが1980年代後半からは国内でもPanasonicを使うようになっていた。白物家電では「National」の認知度が高かったからだ。

パナソニック株式会社は大阪府門真市に拠点を置く世界的な電気メーカーで、国内では日立製作所、ソニーに次いで3位で、38の事業部からなる社内カンパニー制を採用している。アプライアンス社、ライフソリューションズ社、コネクティッドソリューションズ社、オートモーティブ社、インダストリアルソリューションズ社、中国・北東アジア社、US社の7カンパニーである。連結対象は592社、これら関連会社も含めて、家電の他にも産業機器・住宅設備・環境関連機器など電気機器を中心に多角的な事業を展開している。創業以来消費者向け製品・サービスに力を入れてきたが、2013年から企業向け製品(BtoB)の比率を上げていく方向へと舵を切っている。現在売り上げ全体に占める家電の割合は24%である。松下電工の合併および三洋電機を連結対象とする現在は、車載設備・住宅設備・エネルギーマネジメント機器などをコアとして成長戦略を加速させている。グローバル展開ではアビオニクス、カーナビなどのIVIシステム、車載用リチウム電池、換気扇、コードレス電話、業務用冷蔵庫で世界一位のシェアを誇る。国内では唯一全部門を網羅する総合家電メーカーで家電業界の多くの部門でトップシェアを有し、家電以外でも電池、住宅用太陽光発電機、照明器具、電設資材、ホームエレベーター、電動アシスト自転車で国内一位のシェアとなっている。また知財活動にも秀でており、パテント・リザルト社の「特許資産規模ランキング」で2017年は二位となっている。

パナソニックミュージアムのこと
1918年(大正7年)松下電気器具製作所の創立以来100年。パナソニックは創業者・松下幸之助の経営理念「企業は社会の公器」を確立して、その事業を通じて社会に貢献することを実践してきた。企業活動の枠を超え、広く人類の繁栄と幸福を願いその実現に情熱を傾けてきた。そこには、より良い暮らし、よりよい社会を求め続けた松下幸之助の高い志、「生き方・考え方」を数多の後進が継承し、数々の製品・技術を生み出してきたパナソニックならではの企業文化が息づいている。「パナソニックミュージアム」は2018年3月に創業100周年の社会や消費者への感謝を表すとともに、松下幸之助の言葉や、歴代の製品に触れながら、その熱き思い、パナソニックの“心“を未来に伝承していくことを願って開設された。施設は大阪府門真市にある本社敷地内に建設された。京阪本線の西三荘駅から徒歩2分に位置する。施設の全体配置計画は、「松下幸之助歴史館」、「ものづくりイズム館」そして2006年にオープンした「さくら広場」で構成されている。創業50周年のとき「松下電気歴史館」が創設されていて、ほぼ50年ぶりのリニューアルである。「松下幸之助歴史館」の前には「創業者松下幸之助翁寿像」が立っている。建築は丸窓が特徴的な外観で1933年に門真に建てられた本店・工場をそのまま模したもので船舶を連想させる近代建築である。敷地も本店跡地そのままで、当時の意匠をより正確に再現している。屋根にある煙突や舵輪のオブジェも当時のままである。舵輪は松下電器の進路を定める本店の使命を象徴するものである。展示室は「松下幸之助に出会える場所」として「道」をコンセプトに幸之助94年の生涯をたどる展示計画となっている。時代軸と事業軸でその生涯を追っていくものである。写真パネルで幸之助が何を考え、どういう行動をしたのかを展示している。

展示各所には幸之助の名言とそのもととなった文章を示した「松下幸之助のことば」カードが用意され見学者は自由に持ち帰ることができる。展示構成は1章1904年〜礎から7章1968年〜経世で構成されている2章1918年〜創業の展示空間に旧歴史館に在った「創業の家」のレプリカが移築されている。これはまだ松下幸之助が存命の頃に造られたものなので、細部まで往時の様子が再現されている。薄暗い展示は当時の家屋の照度を再現しているためである。家の中には”もう一人の創業者妻・むめの”とアタッチメントプラグの材料を混ぜて釜で煮ている“むめ”の弟 井植歳男(のちの三洋電機創業者)そして土間には松下幸之助が座っている、創業時のシーンがマネキンでディスプレイされていて、旧歴史館の頃から社員教育に使われていた。5章1961年〜飛躍の展示から高度成長期に製造されたテレビ、洗濯機、冷蔵庫などの家電製品が展示されている。6章1961年〜打開では1964年の「熱海会談」が展示され印象的である。7章1968年〜経世では晩年に至って「明日の指導者を育成する」を目指し、1978年に開塾した松下政経塾が展示されている。社会に様々な貢献を果たした松下幸之助は1989年、昭和が終わった年に94歳で亡くなった。この展示室に併設されたライブラリーでは、紙資料2万点、書籍1200冊、写真やネガ3万枚、音声2000本、映像5000本などパナソニックの100年にわたる歴史資産をデジタルデータ化し、閲覧が可能となっている。閲覧端末はスロットに「松下幸之助のことば」カードを差し込むとカードの言葉に関連した資料にスピーディにアクセスできるようになっている。壁面は松下幸之助の著書と関連する書籍がその解説とともに展示されている。
「ものづくりイズム館」は旧歴史館の建物そのものなので外観は同じである。展示テーマは「パナソニックの“ものづくりDNA”を探る」で、人々の100年の暮らしの変化とともに歩んだ歴代の製品約550点が展示される。エントランスにはナショナル坊やと歴代のロゴが彫られたレリーフパネルがあり、続くストレージギャラリー(収蔵庫)はそれぞれのジャンルの一号商品やデザイン家電がまとめられそれぞれのパッケージの連続で展示されている。川島氏がデザインした家具調テレビも展示されている。ストレージギャラリーの先にあるのはマスターピースギャラリー、「思いやり」「感動」「安心」「新定番」「家事楽」「自由」の6つのテーマで構成されていて、それぞれの分野の「マスターピース」が展示されている。デジタル・ムーバP201HYPERはデジタル方式携帯電話で初めて100gを切った、当時世界最小最軽量の携帯電話だった。モバイルノートPC「レッツノート」は今も改良を重ねながら発売されている。ロングセラーの「ハイ三角タップ」「ハイトリプルタップ」も展示されている。展示空間の最深部にあるのはヒストリーウォールで、横16m・縦2.2mの636インチスクリーンである。8K映像で100年間の製品を一望できる映像展示となっている。スクリーンの下には「宣伝・広告の100年」がパネルで展示され一覧できる。
「ものづくりイズム館」から道を挟んだ向かい側には今回見学できなかったが「さくら広場」がある。ソメイヨシノが190本植えられていて、地域貢献の一環として無料開放されている。広場の中の築堤には1933年に門真の地に本社・工場を移したときに新築された松下幸之助門真旧宅と大観堂がある。これは創業期から松下幸之助の良き心の支えとしてパナソニックの発展に寄与した真言宗醍醐寺派の僧侶加藤大観師の遺徳と功績を偲び、1956年に建立されたもので、いずれも限定公開である。

川島さんのこと
今回のゼミを主導してご案内いただいた川島さんのことに触れてみたい。川島さんは1944年神戸市生まれである。大阪府立西野田工業高等学校・工業デザイン科を1962年に卒業している。大阪府立西野田工業高校は大阪府立の職工学校として1908年に現在の福島区大開にお開校した。大阪府内の工業高校としては大阪府立都島工業高等学校とともに一番古い歴史を持っている。1941年に大阪府立西野田工業高校へと改称し1948年に学制改革により、大阪府立西野田工業高等学校と改称し、現在に至っている。川島さんは卒業後、松下電器産業に入社した。1965年(昭和40年)10月当時一世を風靡した家具調テレビ「嵯峨」のデザインなどを担当した。「嵯峨」は北欧デザインに影響されたが、米国のテレビ受像機の模倣ではなかった。当時すでに松下電気デザイン部は、海外のデザイン情報を取り入れて、日本独自のデザイン開発を推進できる状況にあったのだ。「嵯峨」のデザインはステレオ「宴」に影響され、「宴」はステレオ「飛鳥」に影響された。余談だが「飛鳥」は「校倉造」のイメージがつけられているが日本調を狙ったわけではなく、宣伝によってつけられたイメージである。「ホワイトグッズ(白物家電)」に対して、木を用いたものは「ブラウングッズ」と呼ばれ、他社のデザインにも影響を与えた。その後周囲の強い要望により、若干20歳で労働組合に従事した。当時の労使関係は混迷を極めていた。その安定化と労働組合の近代化を目指して川島氏は寝食を忘れて取り組んだ。「賃金闘争だけではなく、一市民として地域社会を良くする義務がある。この時の川島氏はそういった労働組合を「目指して取り組んでいたのだ。専従を含む組合活動は28年に及んだ。その間の活動は、淀川の水質浄化、都市の緑化、電力不足、エアロビクス運動の提唱、関西国際空港建設の推進など市民生活に直接関係する課題を取り上げてきた。社会を構成する一因としての責任と自覚を持って組合活動を推進した。また民労協のヨーロッパ旅行がきっかけとなり、桜の並木道をヨーロッパにも作ろうと寄付を募り、パリ、ロンドン、ローマ市長に桜の苗木をプレゼントした。「これからの労働組合は、文化的な面での社会貢献も果たさなくてはならない。」という思いからであった。このような機運の中から出てきた課題が、大阪で廃れつつあった歌舞伎を復興させるという課題である。1977年(昭和52年)大阪歌舞伎座で澤村藤十郎襲名披露公演が開かれたが、入りが悪く大阪顔見世は9回で打ち切られた。澤村藤十郎がなんとか大阪で歌舞伎を復興させたいと頼ったのが当時川島氏の上司であった大阪労協代表(松下電器労組合長)の高畑敬一郎であった。高畑から上方歌舞伎の復興支援を依頼されたことが川島氏の歌舞伎との出会いであった。松下電器の創業者松下幸之助の言葉に「不況もまたよし」という言葉がある。不況の時こそ気持ちを引き締め、反省する。そこから新しい挑戦のチャンスが生まれる、ということだ。澤村藤十郎襲名披露公演の不入りが「関西で歌舞伎を育てる会」を誕生させ、川島氏との出会いも生んだわけだ。松下幸之助氏は川島氏にとって尊敬して止まない人生の師である。仕事や労使協議の場を通して、物の見方や考え方の多くを学んだ。「関西歌舞伎を愛する会」は1993年(平成4年)に「関西で歌舞伎を愛する会」に名称を変更した。川島氏は1994年からパナソニック映像の社長に就任した。赤字会社を三つ集めて作った会社を2年で黒字にし、8年8か月社長を務めた。「人生に無駄な経験などひとつもない。全ては次のことに生かされる。」この教えも創業者から学んだ。松下幸之助氏は父が米相場に失敗し、9歳で大阪に丁稚奉公に出た。父が米相場で失敗しなかったら松下電器は存在しかった。川島氏は三宮で生まれ、父は大きなクリーニング店を営んでいたが、戦争で全てを失い疎開した茨城では雨漏りしても受け皿がないほどの貧しさだった。そこから何をするにも必死で頑張ってきたわけである。創業者松下幸之助にオーバーラップする川島氏の原点である。

松下デザインからパナソニックデザインへ、
日本の現代デザインは、第二次世界大戦後に開化したといえる。1946年から通産省(現、経済産業省)は工芸技術産業試験所の活動を機関誌「工芸ニュース」により広報し、海外市場調査(現、JETRO)を設立して、輸出振興の観点から海外デザイナーの招聘や海外へのデザイン留学生の派遣を積極的に行った。1952年には日本インダストリアルデザイナー協会(JIDA)が設立され、そのデザインコンペティションはインダストリアルデザイナーの登竜門となり、1954年発売の天童木工のバタフライ・スツールで知られる柳宗理やマツダ三輪自動車K360の小杉二郎などを輩出した。また東京芸大教授の小池岩太郎を中心として組織され、ヤマハのオートバイYD1型のデザインに参賀したGKインダストリアルデザイン研究所などのデザイン事務所もこの時期多く設立された。どGKの栄久庵憲司によるキッコーマン醤油の卓上瓶は今でも語り継がれている。「もはや戦後は終わった」と経済白書が宣言したこの時期、食事の所作を変えたこの卓上瓶は、デザインが新しいライフスタイルを提案したものと言える。
パナソニックデザインのルーツは1950年代までさかのぼる。1951年に初めてアメリカ市場視察を行い帰国した創業者の松下幸之助が飛行機のタラップを降りるや「これからはデザインの時代やで」と言った話は有名である。当時のアメリカで、ビジネスの決め手がデザインになっている現場を目の当たりにしてきたのだ。松下幸之助氏はすぐに、当時千葉大学工業意匠科講師であった真野善一氏を招聘し、松下電気に「宣伝部意匠課」を3名配属し設置した。それは日本で初めての企業内デザイン部門の誕生であった。真野は1916年(大正5年)生まれで、東京高等工芸学校工芸図案科を卒業、商工省陶磁器試験所、高島屋東京支店設計部などに勤め、昭和25年に千葉大学工学部教授となった後、昭和26年に松下電気工業デザイン部宣伝部意匠課長に迎えられたのだ。
扇風機20B1は、真野による初の「松下デザイン」であり、これ以降あらゆる製品のデザインが製品意匠課に持ち込まれるようになった。1953年にはラジオDX-350が新日本工業デザインコンペで特選2席を受賞し活躍した。当時はデザインプロセスへの理解の無さから、「その場ですぐやってくれ」という無理な依頼も少なくなかったが、しだいに製品開発段階からデザイナーが関わることを求められるようになり、デザインとは表面的なスタイリングのみを表現するのではなく、製品が使われる場所や使われ方も含めた設計思想であるということを理解してもらおうと努めて活動することになる。パナソニックデザインとなっても、この黎明期の活動、思いをDNAとして継承しながら、今日に至っている。

結びとして、余話として、
今回のパナソニックミュージアムの見学を終えて、産業革命以来、近代から現代への160年にわたるデザイン、その中でもプロダクトデザインの歴史的変遷を追いかけ、製品デザインの基本ルールやデザインがどこに向かっていくのかを解き明かしてみたいと思った。
日本におけるデザイン草創期のエピソードを幾つか上げてみたい。エポックメイキングなデザイン製品、キッコーマン醤油の卓上瓶にもどる。当時、日本の一般家庭では、一升瓶入りの醤油を買ってきて保存し、食卓で醤油さしに移し替えて使っていたが、注ぐたびに口から垂れて食卓にシミを作ってしまうという問題があった。野口醤油醸造(現、キッコーマン)は「新しい醤油の形」を新進デザイナー栄久庵に依頼した。残量が分かる透明のガラスと醤油本来の色をイメージさせる赤いキャップを採用し、安定感と詰め替えを意識して底部口部は大きく、中間部は女性の持ちやすさと注ぐときの手の形の美しさを考慮して細くしたとされる。注ぎ口の下側を細くして液誰もなくなった。食事の所作を変えたこの卓上瓶は、新しいライフスタイルを提案したものと言える。その後神武景気に沸いた時期には、自動車の生産も再開され本格的なモデルが登場した。トヨタが「designの勝利」と広告したコロナ、日産のダットサン310(初代ブルーバード)、富士重工のスバル360などが上げられる。家電でもシンプルなモダンデザインとして、1955年発売の東芝の電気釜ER-4や東京通信工業(現ソニー)のトランジスタラジオTR-610などが注目された。東芝の電気釜はネーミングとして「電気炊飯器」ではなく「電気釜」とすることで「釜の過熱手段が燃料から電気に変わっただけ」という安心感を消費者に与え、従来のかまど口をイメージさせる黒い台形の操作部を採用し、デパートでの実演販売でおいしごはんが「科学的」に自動で炊き上がることをアピールした。東芝はネーミング(視覚・聴覚)、デザインモチーフ(視覚)、実演(味覚・聴覚・臭覚・触覚)など、消費者の五感を総動員させるマーケティング手法を駆動させたのだ。これも新しい経験とライフスタイルをデザインした事例である。本田のスーパーカブC100もこの時代の製品で、以後2008年までシリーズ全体で6000万台売り上げた。1957年には、通産省に意匠奨励審議会が設置され、グッドデザイン(Gマーク)商品の選定事業が開始され、翌年にはデザイン課が設置されて、デザインの奨励、振興の体制が国として整備された。1960年世界デザイン会議が日本で開催され、各分野のデザイナーや建築家が対等に議論を闘わした。その経験は1964年東京オリンピック、1970年日本万国博覧会に活かされていった。また1970年代、1980年代にかけては広告・デザインが大きく変わったことは他でも述べている。新聞広告をテレビ広告が追い抜いたのは1975年であった。その前年に日本広告審議機構が発足して、広告の社会的役割が問われると同時に、広告表現の芸術性の追求が盛んになった。消費者の価値観やライフスタイルに「焦点を「あてて、企業ポリシーへの共感を得ることに重心が移っていった。商品と直接関係無しない映像・音楽を流す「イメージ広告」が表現の主流となっていった。糸井重里や中畑貴志などのコピイライターが脚光を「浴びた時代であった。西武系のファッションビル「パルコ」は1974年渋谷店を開店し、大胆なビジュアルと印象的なコピーのポスターを中心に、渋谷の街全体を媒体とする広告展開をし、それと前後して西武劇場(現PARCO劇場)開設や「ビックリハウス」創刊などの文化事業を展開して企業イメージを高めていった。この総合的な戦略は80年代のCIブームとなって社会に広まっていった。ケンウッド、日本たばこ産業、アサヒビール、JRなどがその導入例である。
さらに海外のエピソードを追ってみたい。ドイツにBRAUNという家電ブランドがある。日本ではシェーバーや電気歯ブラシでおなじみであるが、ドイツでは幅広く家電製品を製造していてグローバルに展開しているメーカーである。ブラウンはデザイン性の高いプロダクトデザインで他の多くのメーカーから尊敬されていて、あのAPPLEもブラウンから影響を受けていると言われている。ブラウンは「家電デザインのルーツ」と呼ばれているのだ。その理由は創業からの歴史にある。1921年にマックス・ブラウンによって創業され、最初は工業用機械のベルトを固定する工具の販売から始まった。最初の自社製品はHi-Fiラジオである。1930年代に入るとドイツを代表するラジオメーカーへと成長する。第二次世界大戦の間は、家電機器が製造できなくなるがその間ブラウンは様々なアイディアを温めており、戦後はジューサーやクッキングミキサーなどのキッチン家電を相次いで生み出した。1951年マックス・ブラウンは急逝し、その経営は技術者のアルトゥール・ブラウンとビジネス学位を取得していたエルヴィン・ブラウンの二人の息子に引き継がれた。ブラウン兄弟は「人に対する尊厳」というビジョンを掲げ、高いデザイン性と機能性を持つ優れたプロダクトを生み出していく。

川島さんのことにもどる。川島さんの名刺には、「関西歌舞伎を愛する会」事務局長という肩書の下に、こんな言葉が記されている。「他人のために生きた人生だけが、価値を持っている。」(アルバート・アインシュタイン)川島さんの半生はまさにこの言葉通り「ボランティア活動のために生きた人生」であったのではないか。「関西歌舞伎を愛する会」」大阪で開催された「国際花と緑の博覧会」、「南米ペルーでの小学校の寄贈」この三つが活動の柱である。松下電器産業に入社後テレビなどの製品デザインを担当した後、若干20歳で乞われて労働組合活動に従事。当時混迷する労使関係の安定化と労働組合活動の近代化に寝食を忘れて取り組んだ。「賃金闘争だけでなく、一市民として地域社会を良くする義務がある。」そういった組合活動を続けたのだ。「これからの労働組合は、文化的な面での社会貢献も果たさなくてはならない。」松下幸之助から、松下のデザインから多くを学んだ川島さんの言葉である。今回のゼミナールも川島さんとのご縁から、多くの学びと気づきを頂いた。「温故知新」
はじめに
2019年12月、緩やかな暖冬の中今年最後となるMCEI大阪定例会を向かえた。今回のテーマは、みらいごはんー2050年の食生活を支えるしくみ創りーである。MCEI大阪には2000年以降20年間協力いただいている田中浩子氏の登壇である。田中氏は立命館大学 食マネジメント学部で教授を務めながら、「八剣伝」でおなじみのマルシェ株式会社と業務用冷凍庫を製造するフクシマガリレイ株式会社で社外取締役を「担っている。「栄養」と「経営」二つの視点から「社会実装研究」をまさに実践している。30歳代前半にフリーランスの栄養士としてスタートした時、栄養士の「マーケティング力の弱さ」であった。「食べる楽しさと大切さを伝えるしくみ創り」これが田中氏の現在に至る原点となっている。

ここで今回のテーマに在る2050年を展望してみたい。世界人口は現在の77億人から2050年には97億人、2100年に109億人に増加すると推計する報告書が国連によって発表されている。同時に2100年をピークとして減少し始める可能性も指摘している。この50年までの増加のうちインド、ナイジェリア,コンゴ(旧ザイール)など9カ国が全体の50%超を占める。インドの人口は27年頃中国を抜いて世界一となる見込みである。環境・気候変動については、人為的な温室ガスの排出量が2030年まで増え続け、2030年をピークに減少するものの、炭素循環フィードバックやアイス・アルベド・フィードバックなど気候プロセス上の要因も加わり、2050年までに3度上昇する。1.5度の上昇で西南極の氷床が融解し、2度の上昇でグリーンランドの氷床が融解する。2100年には18世紀の産業革命前に比べて6度〜7度上昇するという悲観的な予測を出すフランスの研究者もいるが、2060年までにカーボンオフセットにより相殺が可能となれば、1.5度の上昇にとどめられる。こうした異常気象は食料の供給を不安定にし、人口が97億人に達すると予測される2050年には穀物価格が最大23%上昇する可能性も指摘される。ただ単純に農地を増やせるかといえば、そうでもなく農業は異常気象の影響を受ける一方で、家畜を飼育し窒素肥料を使用することで、大量の温室ガスを出す、排出源でもあるのだ。技術では2045年にAIが人類の知性を上回るシンギュラリティに到達し、2050年に地球と宇宙をつなぐ「宇宙エレベーター」が実現、脳に電気信号を読み取るチップの埋め込みが普及、目の細胞に外部信号を送ることで、盲目の人が見えるようになる、富裕層は子供の遺伝子構造を選択できる、など様々な分野で予測されるが実現の振幅は大きいと思われる。これを進歩と単純にとらえられない複雑な様相である。

2050年の世界経済は
ここで2050年に向けての世界経済について触れておく。2042年までに世界経済の規模は倍増する。中国はすでに購買力平価(PPP)ベースのGDPが米国を抜き世界最大の経済大国になっている。購買力平価とは為替レートの決定メカニズムの一つで、ある国の通貨建ての資金の購買力が、他の国でも等しい水準となるように、為替レートが決定されるという考え方。モノの価格に注目して外国為替レートの変動を説明する理論で、1921年にスエーデンの経済学者、グスタフ・カッセルが提唱した。英語の「Purchasing Power Parity」の頭文字を「とってPPPと呼ばれている。また市場為替レート(MER)ベースでも2030年までに世界最大となる。
2017年2月以降世界の経済は現在の先進国から新興国へシフトする長期的な動きが2050年まで続くと見込まれている。2050年までに主要経済大国7カ国の内6カ国は現在の新興国が占める見込みである。2050年までにインドは米国を抜き世界第2位、インドネシアは第四位の経済大国となり、日本、ドイツなどの先進国を抜き去る見込みである。ベトナムは2050年までに世界で最も高成長を遂げる経済大国となり、予測されるGDPの世界での順位は第20位に上昇する。コロンビアとポーランドは、それぞれの地域(中南米とEU)で最も高成長を遂げる経済大国となる可能性がる。トルコは、政治不安を払拭し経済改革を推進すれば2030年までにイタリアを抜く可能性がある。ナイジェリア、南アフリカ共和国、エジプトは自国経済の多角化、ガバナンス水準向上、とインフラ改善の前提条件を実現すれば年平均成長率4%前後の成長を2050年までの間維持できる。EU加盟国27カ国の世界GDPに占める割合は2050年までに10%未満へと低下するが、英国は、Brexit(ブレグレジット)後も貿易、投資、人材の受け入れにオープンであれば、成長率においてはEU27カ国平均を長期間上回る可能性はある。世界経済は今後2050年までに年平均実質成長率約2.5%のペースで成長し、その経済規模は2042年までに倍増すると予想される。その成長の主な牽引役となるのは、新興市場と開発途上国となる。E7(ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、ロシア、トルコの新興7カ国)は今後34年間、年平均3.5%のペースで成長し、G7(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、イギリス、アメリカ)はわずか1.6%程度の成長にとどまる。E7のGDPにおけるシェアは2050年までに約50%上昇し、G7のシェアはわずか20%強にまで縮小する。ただ一人当たりのGDP順位は、2050年でもE7よりも高くなる見込みで、新興国の所得格差が収斂するのは2050年以降も時間が掛かる見込みだ。しかし、技術革新が高度なスキルを持つ人材と資本家に優位に働くことから、各国の所得格差が拡大し続ける可能性もある。
世界経済の成長は2020年まで年平均3.5%で推移したあと鈍化し、2020年代は約2.7%、2040年代は約2.4%と予想される。これは多くの先進国が労働人口の著しい減少に見舞われるためで、同時に新興国の市場が成熟し、キャッチアップ型の急成長が困難となり、成長率が鈍化するのだ。新興国は自国の潜在力を実現するために、教育・インフラ・技術への持続的で効果的な投資が必要となる。新興国経済の多角化が重要であり、政治、経済、法律、社会面の諸制度を確立しイノベーション、起業家精神の創出に取り組む必要がある。

食料自給率について
日本の食料自給率は2018年度、過去最低にまで落ち込んだことが明らかになった。日本の食料生産は危機的な状況に陥りつつある。一方世界では、旱魃や豪雨などの異常気象が頻発し、食糧生産が不安定になることが指摘されている。食糧自給率とは国内の食料消費が国産でどの程度賄えているかを示す指標で、総合食料自給率と品種別食料自給率の二種類があり、基本的には総合食料自給率のことを指す。この総合食料自給率は熱量で計算する「カロリーベース」と、金額で計算する「生産額ベース」があり、日本ではこの二つの基準が長期的に低下している。2017年度の指標だが、日本のカロリーベース総合食料自給率(一日一人当たり国産供給熱量を一人一日当たり供給熱量で割った指標)は38%であった。この時点で私たち日本人は食べ物の62%を海外からの輸入に頼っていることになる。ちなみに生産額ベース(食料の国内生産額を食料の国内消費仕向額で割った指標)は66%であった。他の先進国に比べても、日本の水準は最低である。食料自給率トップのカナダは200%を超え、続くオーストラリア、アメリカ、フランスも100%を超えている。しかし、品目別食料自給率で見ると、日本も米は100%、野菜は79%自給しており、全ての食料を輸入に依存仕手いる訳ではなく、また生産額ベース(66%)で自給率を考えると、日本と他の先進国の差は縮小する。
第二次世界大戦終戦直後の1946年度(昭和21年)の日本の食料自給率は88%で、その後緩やかに下降し続け1989年(平成元年)に50%を割り込み、2000年代に入り40%前後の横ばいで推移したが2017年度に38%に下降したのだ。日本の食料自給率の低下の原因は、戦後の復興に伴い国内生産が主であった米・野菜が中心の日本食から欧米化した食事にシフトしたことから、海外からの輸入による小麦や飼料や原料の多くを輸入に頼る畜産物(肉類)や油脂類の消費が増加したことである。まさに“食生活の変化”がその大きな要因となったのだ。中でも飼料を含む穀物全体の自給率の低さは日本の特徴としてあげられ、特に畜産物(肉・卵・乳製品)に影響を与える例えば牛肉1㎏にはその10倍の11㎏の穀物飼料が必要なのだ。この飼料を含む穀物全体の自給率は28%である。
田中氏によると日本の食生活は第二次世界大戦後に大幅な改善がなされた、戦後の飢餓・低栄養からの脱出である。その後1975年(昭和50年)頃から米飯を主食として、魚介類と肉類を半々に出現させ、季節の野菜や乾物類を副菜とし卵、牛乳を加えた変化に富んだ献立を作り出した。「一汁一菜」、「一汁三菜」の日本型食生活の確立で、これは世界でも評価された。1964年の東京オリンピックの選手村でのメニューやNHKの「今日の料理」などもこの「日本型食生活」の確立に貢献した。しかし平成に時代が変わっての30年間は生活習慣病の増加など、「日本型食生活」は新たな課題を突き付けられている。

消費ではなく持続可能な生産へ
今、世界の政策立案者は、長期的かつ持続的な成長を実現するために、多くの課題に直面している。高齢化・気候変動などの構造的な変化に対応するために、持続的に社会貢献できるような労働力の育成や、低炭素技術の促進など、未来を見据えた政策が必要となる。世界貿易の成長鈍化、所得格差の拡大は多くの国で、地政学上の不確実性を増大させている。広範囲な産業で多くの人に機会が提供されるよう、多様性に富んだ経済の実現が急がれる。
世界のエネルギー消費量が2050年に2010年比で80%増となる可能性が予測される。このまま温室効果ガスの排出が増え続け世界の平均気温が18世紀の産業革命前に比べて3〜6度上昇すれば、人類は地球という閉じられたグローブの中で生存のための閾値を狭めていくことになる。人類は、はるか紀元前から文明を育み始めた。その暮らしの起源より、生きられる場所で暮らしてきたのだ。生物としての人は当然生きられる場所、環境でしか生きられる訳がないのだ。人類は食料増産のために数千年にわたり森林を切り開らいて農地に転用してきた。今後さらに森林を伐採すれば、その影響は農業生産に直接跳ね返ることも事実である。今後農業生産の現場には、温室効果ガスを減らす努力を益々求められていく。
日本の国土面積の約7割は森林が占めていて、農地として利用できる面積は限られている。一人当たり農地面積は近年の宅地等への転用と耕作放棄地の増加により、農地面積が最大であった1961年(昭和36年)に比べて、25%減少している。まずは耕作放棄地を蘇らせることが大切だ。農業従事者も2017年時点で平均年齢が67歳と高齢化が進み、新規就農支援制度の充実や農業法人への就職促進など官民で人材確保への取り組みが必要である。この人材確保と同時にロボット技術やICT,AIなどの先端技術を活用した「スマート農業」の実現促進も重要である。また私たちが暮らす地域は、それぞれの土地の気候・地形等の環境に適した食物が栽培され育ってきた。一人一人が地元で獲れた食材を食し、「地産地消」に取り組むことも、日本の食料自給率向上には有効な手立てである。2050年に向けて田中氏は“2050年食生活未来研究会”を立ち上げ活動を始めている。不確実性に富む現在の状況の中では、未来を正確に予測することよりも、それぞれの地域の主体者自らが、望ましい自分の目的に向け、未来を創造していくこと、自分が思い描く“世界“を築いていくことが大切だと語る。まさに”気づくから築く“である!また人口減少社会における生活者としての「マインドセット」も必要であるという。この思考は食を起点とした街づくり、持続可能な街づくりへと続いていく。すでに福井県の小浜市は2001年9月に「食のまちづくり条例」を制定し、2004年には「食育文化都市」を宣言し、食の街づくりを推進している。小浜市は、豊かな自然から得られる食材を、飛鳥、奈良時代には朝廷に献上し、伊勢・志摩、淡路とともに「御食国」(みけつくに)と呼ばれてきたのだ。

また、日本の食生活は、食べ残しを足元から減らすことも大切で、日本では年間1900万トンも廃棄している。世界では約10億人。7人に1人、アフリカでは3人に1人が飢餓の状態であることを考えれば「食」に対する考え方を改めていくことは、人類の喫緊の課題ともいえる。
最後に、少し長くなるが、私が大きく影響を受けた中尾佐助氏(遺伝育種学・栽培植物学 専攻)の文章を紹介しておきたい。
「文化」というと、すぐ芸術、美術、文学や、学術といったものをアタマに思い浮かべる人が多い。農作物や農業などは“文化圏”の外の存在として認識される。しかし文化という外国語のもとは、英語で「カルチャー」、ドイツ語で「クルツール」の訳語である。この語の元の意味は、いうまでもなく「耕す」ことである。地を耕して作物を育てること、これが文化の原義である。これが日本語になると、もっぱら“心を耕す”方面ばかり考えられて、はじめの意味がきれいに忘れられて、枝先の花である芸術や学問の意味の方が重視されてしまった。しかし、根を忘れて花だけを見ている文化観は、根なし草にひとしい。文化の出発点が耕すことであるという認識は、西欧の学会が数百年にわたり、世界各地の未開社会に接触し調査した結果、あるいは考古学的研究、あるいは書斎における思索などを総合した結論である。人類の文化が、農耕段階にはいるとともに、急激に大発展を起こしてきたことは、まぎれもない事実である。その事実の重要性をよくよく認識すれば、“カルチャー”という言葉で、“文化”を代表させる態度は賢明といえよう。・・・・・中略・・・・人類は、戦争のためよりも、宗教儀礼のためよりも、芸術や学問のためよりも、食べる物を生み出す農業のために、いちばん多くの汗を流してきた。現代とても、やはり農業のために流す汗が、全世界的に見れば、もっとも多いであろう。過去数千年間、そして現在もいぜんとして、農業こそは人間努力の中心的存在である。このように人類文化の根元であり、また文化の過半を占めるともいい得る農業の起源と発達を眺めてみる必要がある。

農業を、文化としてとらえてみると、そこには驚くばかりの現象が満ち満ちている。ちょうど宗教が生きている文化現象であるように、農業はもちろん生きている文化であって、死体ではない。いや、農業は生きているどころでなく、人間がそれによって生存している文化である。消費する文化でなく、農業は生産する文化である。
会員様、はじめご理解とご協力いただいた皆様に、
本年もMCEI大阪の活動を支えていただきありがとうございます。来年もよろしくお願いいたします。
はじめに
未来の消失?現在の矛盾。
今年もあと少し、11月の定例会は恒例となった日経BP総研 品田英雄氏の講演である。
ヒット商品ベスト30を見ると、年々商品の差異が曖昧となり溶け合っている様に見えるがその背景は深淵とも思える。モノもサービスもコンテンツもあり余り、新しいサービスが次々と登場し、企業は商品開発において困難な状況にある。何をどのように提供するかが難しくなっているのだ。日本人の消費スタイルは1970年代に過渡期を経て現在に至っている。70年代は商品が品質訴求から、イメージ訴求へと変わっていった時である。品質訴求の時代は「モノ」そのものの「良し悪し」をつたえ、新しき良きモノを売れば良かった。そこには新しい情報があるから、消費者もその情報を待っていてくれた。
次にくる1980年代から企業が生み出す製品の品質が上限に近くなっていく。言い換えると、メーカーが生み出す製品の基本品質の差が無くなり横並びとなる。品質が微差となると「モノの良し悪し」が届かなくなり、訴求ポイントは、「モノ」から「コト」へと移行した。消費者は「好き」か「嫌い」かで、商品を選択するようになった。商品はイメージ化に向かい、工業製品であってもファッション化せざる得なくなった。

ここで時代を60年代に戻してみる。1958年から50年位の間に日本人の「心のあり方」に表には表れにくいが大きな転換があったのではないかという仮説がある。1950年代、60年代、70年代位までは青年たちにとって現在よりもずっと素晴らしい未来が必ず来るといった、「当然の基底感覚」が確かにあった。それがどの様な未来であるかについて、イデオロギーやヴィジョンが対立し、世代間で闘われてもしていた。しかし21世紀の現在このような「未来」を信じている青年はほとんどいない。1973年以降5年ごとに行われてきたNHK放送文化研究所による「日本人の意識」調査のデータによると、現在日本を構成する世代を15年ごとに「戦争世代」「第一次戦後世代」「団塊世代」「新人類世代」「団塊ジュニア世代」「新人類ジュニア世代」と分類し、各世代の各時点の意識の変化を示す表があり、この表で「星座」のように見える一つ一つの塊は調査時点の「意識」の在りかを点で表示し結んだものである。この「世代の星座」が最近になるほど接近しているという事実が浮かび上がる。「戦争世代」と「第一次戦後世代」と「団塊世代」の意識は大きく離れているが、「新人類世代」と「団塊ジュニア世代」は一部が重なり、「団塊ジュニア世代」以後はほとんど混じりあっているのだ。現在における世代間の精神の「距離」は「新人類」以降差異をなくしているのだ。1970年代にあった大きな「世代の距離」が80年代末に著しく減少し、今世紀に入ってほとんど「消失」しているのだ。「70年代以降に生まれた世代の間で感覚の差異が無くなってきている。」この事実はファッション界でも、教育の現場でも商品開発の現場でもすでに語られてきたことである。
品田氏が上げる社会変革のためのキーワード
今回、品田氏は商品開発において、三つの社会的課題を挙げている。高齢化、非婚化、多文化共生である。

まず高齢化についてである。世界的な高齢化傾向によって、世界の人口動態は未知の領域にさしかかり、世界の人口と社会が変化している。この強烈な実態による社会経済的負担は専門家や政策立案者に警鐘を鳴らしている。元米国国務長官のピーター・ピーターソンは人口高齢化を「化学兵器、核拡散、人種間紛争による脅威よりさらに重大で確実な脅威」と称している。(Peterson1999)
日本は世界でも最も高齢化の進んだ国として突出した地位につけてから35年目を迎えていて、現在、高齢化社会がもたらす大きな社会経済的負担に対応している。2018年(平成30年)時点の内閣府データによると、日本の総人口は1億2632万人でこのうち65歳以上の高齢者は3562万人で、総人口の28%を占めている。高齢化社会の推進要因は人口統計的な要因が強く結合して高齢化の波を突き動かしている。
日本のベビーブーマー世代(1947〜1949年生まれの団塊の世代)が高齢化し、2012年には65歳の通常退職年齢に達することが、日本の人口動態の変化を誘発する要因として大きく働いた。この世代が高齢者になるにつれ、その集団の人口に占める大きさが、日本の人口ピラミッドの形を大きく変えた。また出生率も、この世代の誕生の後は徐々に低下していった。1949年(昭和24年)の第一次ベビーブームには約260万人を超えたが1989年(平成元年)150万人を切り、2065年には56万人まで減少すると見込まれる。人口減少も進み2030年には1億2000万人を割り込み、2055年には一億人を切ると予測される。
この急速な高齢化は日本における主要な公共政策の課題となっている。大きな問題は労働年齢の減少である。1950年では高齢者1人を約12人で支える計算であったが、2015年には高齢者一人を2.3人で、2065年には高齢者一人を1.3人で支えることになると予測されている。経済活動の担い手である労働人口の減少が常態化すると経済にマイナスの負荷がかかり続ける、「人口オーナス」である。逆に高度成長期は生産性の上昇と労働人口増加で成長率が高まる。この状態を「人口ボーナス」と呼ぶ。「人口オーナス」は国内市場の縮小と人々の集積やイノベーションを起こしにくくし、それによって成長力が低下し、労働力不足がワークライフバランを崩し、少子化が更に進行するという縮小スパイラルを引き起こす可能性がある。

二つ目は非婚化についてである。男女ともに高学歴化が進み、大学卒業後一定期間社会経験を積むまでは結婚を控えた方が将来の所得増につながるという説は経済学的定説となっている。女性の社会進出が進む現在では、夫の収入のみに依存するのは女性にとってリスクが高すぎる。また健康状態が良くなって寿命が延びたことも晩婚化の原因と言われている。「健康で体力のあるうちに子供を産み育てなければ」というプレッシャーは極めて少なくなっている。1950年の日本では全体の97%が自宅で出産、出産に伴う生命の危険も高かったという事実を見ても理解できる。社会全体の意識の変化も大きい。30年も遡ると就職する女性の多くは「結婚までの腰掛け」という社会的通念のようなものがあった。この一方的な価値観の押し付けが薄らいだことも晩婚化の原因の一つである。都市部と地方を比較すると、一般に都市部のほうが晩婚化・非婚化が進んでいる。都会だと同程度の学歴や収入のある異性が周りに多勢いるので慌てて結婚する必要性を感じないのだ。「いくらでも相手がいる。」と絶対数が多いことによって誤解するのだ。都心部への人口流入はいまだ止まらないので、「非婚化・晩婚化」は将来的にも進んでいくと思われる。
この次の世代をどのように形成していくかに大きく関わる問題を、性別差の観点から考えてみる。結婚に関する個人主義は「結婚は個人の自由であるから、人は結婚をしなくてもどちらでもよい。」という意識で表現される。他方、結婚に関する伝統主義・保守主義として全ての人は当然結婚するものだという皆婚主義がある。男性については「結婚して一人前」などと表現され、女性については「女性の幸せは結婚にある。」といった意識である。結婚至上主義ともいえるこの意識はどちらも性別役割意識、ジェンダー規範を含んでいる。これらの意識は1990年代後半より、個人主義が強くなり各人の結婚感を非婚へと向かわせる基盤条件となっている。晩婚化、非婚化はどのような階層においても進行した、より一般的な意味を持つ社会変化と言える。これは多くの曲折はあるとしても、基本的には結婚含む社会関係が全体として自立した個人の人間関係へ変化する過程と言える。また女性の社会的地位向上の過程ともいえる。現在の日本では晩婚化、非婚化として表れている。米の第二の人口転換と言われる過程は、同様の本質を持つものであるが、比較的多くの国で同棲が増加し、出生率低下を緩和している点は日本と異なっている。今後日本の社会変化がいっそう進行し、この変化が持続して個人の平等が醸成されていくことによって、晩婚化・非婚化の問題も緩和されていく可能性も現段階では考えられる。

三つ目は「多文化共生」について。日本に暮らす在住外国人は、近年増加の一途をたどっている。外国人登録人口は平成30年末に273万人にも達している。前年末に比べ16万9245人(6.6%)増加となり過去最高である。平成18年3月には、総務省が設置した「多文化共生の推進に関する研究会」が「多文化共生プログラム」を公表し、在住外国人の生活環境整備に向けて省庁横断的な検討が始まっている。経済のグローバル化や人口減少の進展の中、在住外国人の数は今後も増加が予想される。また、在住外国人が日本に定住する傾向が強まるとともに日本で育つ在住外国人の子供も多くなっている。在住外国人への対応については様々な考え方がある、在住外国人はあくまでも一時的な滞在者であり、滞在中の生活についてはそれぞれの母国が対応すべきであるという考え方から、日本社会への同化を求める考え方までである。日本の現状を考えれば多文化共生は、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め、対等な関係を築こうとしながら、共に生きて行くこと」と定義した方が望ましい。すなわち、在住外国人を日本社会の構成員として捉え、多様な国籍や民族などの背景を持つ人々が、それぞれの文化的アイデンティティを発揮できる豊かな社会を目指すことである。
この「共生」という概念に関連して近年注目されるのは、インクルーシブ教育がある。1990年前後からアメリカやカナダを中心に広がり始め、1994年の特別教育に関するサマランカ声明でインクルーシブな学校が提起され国際的な市民権を得た。この教育における考え方は人間の多様性の尊重を強化し、障碍者が精神的および身体的な能力等を可能な限り最大限まで発展させ、より自由な社会に適切に参加することを可能にすることを目的とするものである。障害のある者と傷害の無い者が共に学ぶ仕組みで、インクルージョン教育とも呼ばれる。この教育の実現を通して、共生社会の実現に貢献しようという考え方で、2006年12月の国連総会で採択された障碍者の権利に関する条約で示されたものである。日本でも同条約の批准に向けて2011年8月に障碍者基本法が改正され、「可能な限り障碍者である児童及び生徒が障碍者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮」(16条)を行うことが示された。

結びとして、グローバルシステムの危機、あるいは球の幾何学
日本人の消費スタイルは、物質から非物質へ、所有から共有へ、ブランドと持続的な関係から刹那的な関係へ・・・・というように捉えどころのないものに変化しつつある。「液状化消費」と呼ぶ人もいる。建築家・槙文彦は建築デザインと様式の現状を「モダニズムの後、建築様式はまるで大海原を漂う粒子の様だ。」と表現する。1970年代までの人々の歴史意識、歴史感覚は歴史というものはある速度を持って進歩し発展するものだ。という感覚であった。この感覚には客観的な根拠がある。エネルギー消費量の加速度的な増大という事実である。<「世界エネルギー消費量の変化」環境庁長官官房総務課編>しかし冷静に考えてみると地球という閉じられた環境圏域で、このような加速度的なエネルギー消費の進展を永久に続けられるものではないことは明らかである。人類はいくつもの基本的な環境資源を今世紀前半の内に使い果たそうとしている。われわれのミレニアムは、2001年9月11日に世界貿易センタービルに激突する数分前の航空機に例えられるのでは。生物学者がロジスティック曲線と呼ぶS字型曲線がある。成功したある種の生物種は繁栄の頂点の後、滅亡に至る。地球という有限な環境下の人間という生物種もまたこのロジスティック曲線を逃れることはできない。現実構造である。
1960年代までは地球の「人口爆発」が問題であったが、20世紀末には反転してヨーロッパや日本などの先進産業国では「少子化」が深刻な問題となっている。世界全体の人口増加率の数字は1970年を尖鋭な折り返し点として、以後は急速にかつ一貫して増加率を低下させている。現在は「近代」という巨大な人類の爆発期を経て未来の安定平衡期に至る変曲ゾーンにあると見ることができる。「現代社会」の様々な矛盾に満ちた現象は中国やアメリカのように「高度成長」をなお追及し続ける慣性の力線と、安定平衡期に軟着陸しようとする力線が拮抗するダイナミズムの種々相と読み取れるのでは。

余話として
コトという幻想、もしくは虚構の時代へ、そしてミレニアルへ・・・
高度経済成長期から脱高度成長期に至る時代の青年たちの精神の変化について、現場からの報告として三浦展によるアクチュアルな現場からの報告がある。三浦氏は高度経済成長期の頂点ともいえる1980年代のリッチで華麗なる消費文化を主導してきたPARCOの「アクロス」誌編集長としてこの時代の若者達の動向を定点観測して発信してきた。1990年にPARCOを退社、バブル崩壊後も定点観測を「続け、持ち前の鋭敏な現場感覚で得た情報を発信し続けている。三浦氏の主要な関心は若者たちのライフスタイル、ファッション、消費行動である。高度経済成長期終結後の三浦氏の観測は、2009年「シンプル族にお反乱」(KKベストセラーズ)と2016年「毎日同じ服を着るのがおしゃれな時代」(光文社新書)でまとめられている。キーコンセプトはシンプル化、ナチュラル化、素朴化、ボーダレス化、シェア化、脱商品化、脱市場経済化である。以下この二著からキーワード、項目を挙げてみる。お金があっても質素に暮らすことがカッコイイと思われる。物をあまり消費しない。使わないものをため込むのはもったいないと考える。好きなものだけ部屋に置き、あとは物を買わない。共有で済む物は共有する。手仕事を重んじる。手作りを好み、既製品を自分で手を加えたい、改造したい。暮らしの基本である衣食住を大切にする。便利な物に依存せず、昔ながらの方法で暮らし、大事なものに手を入れる。
自動車離れが進んでいる。自転車の人気が上昇。この消費者達に集まってもらい、どんな商品が欲しいかとインタビューすると「余計なデザインをするな、余計な色を付けるな、余計な機能を付けるな、ゴテゴテさせるな、何もしなくてもいい、普通がいい。」という声ばかり聞こえる。カルチュラル・クリエイティブズ=シンプル族は「進歩(モダン)の終わり」の人間像。大衆消費社会が終わり、シンプルライフ志向が拡大しているのだ。シンプル族の生活志向は1エコ志向2ナチュラル志向3レトロ志向・和志向4オムニボア志向(様々な文化を自由にお生活に取り込んで楽しむ。)5ソーシャル・キャピタル志向である。

1970年は日本万国博覧会が大阪で開催された。この年を基点に高度経済成長期が大きく転換していき、消費経済は成熟化し現在に至るわけである。1980年から2000年まではある意味、時代が尖っていて、この時代の商品も個々に際立ち、尖鋭化して見えたと思う。今、消費社会を主導する世代は1980年から2000年の間に生まれたミレニアル世代である。あらためて今思うことは、実務者は現実の現場に出て定点観測を怠らず、その時々の時代の年縞を明らかにして次の時代に備えることが大事であるということ・・・。
はじめに、川端組長と頼りになる添え木の榊原氏のこと。
2019年10月定例会講師は京都一ファンキーな不動産屋を自称する1977年生まれの株式会社川端組。代表取締役組長 川端寛之氏である。
川端組長は2000年に大学を卒業後、技術専門学校で宅地建物取引士の資格を取得し、その後自由な職場環境に恵まれて不動産業の経験を重ねた後、2014年に起業している。取り扱う物件のユニークなリノベーションを企画提案しながら、感度の高い人やマイノリティの人にも選択肢の幅を広げながら日夜奮闘している。そのリノベーションはシンプルでユニークである。輸送用コンテナや建設現場に使われる単管足場などを、普通は建築設計には取り入れられないデザイン要素を大胆に企画し実現していく。それらはニッチな要望に突き刺さり、余白とブラックな部分に満ち満ちて、建築と街づくりの可能性を広げているように思う。店舗付き住宅が慢性的に不足する中で既存の街を活性化させるために「あきらめたくない、あきらめない。」不動産物件を生み出している。2018年1月より南吹田ファンキーステーションを立ち上げて南吹田琥珀街の街づくりを手掛けている。
今回の定例会は初めての試みとして、榊原允大氏が聞き手に加わっていただき進行した。榊原氏は1984年愛知県生まれで、2007年に神戸大学文学部を卒業している。芸術学部の研修では建築を選択し、2008年に建築リサーチ組織RADを立ち上げて活動を開始している。プロモーションディレクターとして地域の街づくりNPOなどを手助けしている。リサーチの新解釈を提案し、周辺、地域との関わりを重視したユニークなプロジェクトを複数進行させている。2016年から愛知県岡崎市で「おとがわプロジェクト」、兵庫県明石市では明石市立図書館の「ほんのまち明石」の取り組みなどワークショップキットなどを提案しながら進めている。いずれ機会があれば是非聞いてみたい話である。

南吹田琥珀街にもどる。
ことの始まりは2018年に南吹田駅が開業するにあたって、2016年より周辺街区の開発に向けて、設計を担当していた角直弘氏が川端氏に設計図面を見せたことから始まる。多くの開発は最低限の都市計画規制に準拠した上で、住民や近隣の意見をあまり入れずに進めてしまう。南吹田も同じ状況であったが、川端氏がこの業界の定められた流れに異を唱えた。そこで角氏がこれを聞き入れて、企画に川端氏が参加することから始まる。「街をこうしたい、こういう人に来てもらいたい」が描かれないうちに設計図が出来上がっていることへの違和感を川端氏は感じたわけである。成熟社会を向かえても開発の波をかぶっていない街区は貴重で、そこには未来に残したい風景がある。日本の中でも沖縄のはまだその空間が色濃く残ると、川端氏は語る。
東京を代表とする日本の都市は、太平洋戦争直後の焼け野原から、復興期、開発期を経てやがてグローバルな資本、欲望、情報、権力の集中する拠点となり、半世紀を超える。このような時間の中で物的、社会的変化を続け、今日本は21世紀を迎え、成熟期と言われて久しい。これから、どのような都市計画が日本に必要なのか<もう少し規模を縮小して街づくりと言ってもいいが>、どう見ても魅力に欠ける日本の都市や街の景観をどうしていくのか、それを考えていくことが今回の中心テーマだと考える。

高度成長期から成熟期への転換は急激過ぎた転換であったため、今日の日本社会は混乱していると言える。年金や福祉問題、外国人の受け入れを含む人口問題、文化や芸能、<都市や街に伝承されてきた祭りや神事とそれが行われる場所はその多くが無くなっている。>に至るまで関連しながら都市をめぐり、深刻な混乱を引き起こしている。巨大開発やマンション開発、それをめぐる近隣とのトラブル、その調停手法の未熟さ、加えて都市景観の醜悪さも指摘されている。高度産業社会が産んだ<もの>の中にすでに建築も繰り込まれているのだ。このリスクに満ちた都市や街をどのように未来につないでいくのかが問題なのだ。ここで少し時間を巻き戻して、都市計画を考えてみたい。
街づくりの都市計画的処方箋とは
都市計画の処方箋はいくつかに分類される。オーバーオール型は巨大で派手な都市計画の極致である。1960年にブラジルの首都となった、オスカー・ニーマイヤーがデザインしたブラジリアの様に、野原の上に一から都市全体をデザインし実現するのが「オーバーオール型」都市計画だ。高度経済成長期には可能であった、日本では規模ははるかに小さいが郊外型ニュータウンがこの都市計画手法に当てはまる。しかし中国ですら近い将来、いやもうすでに人口の伸びが止まると予想され、世界スケールで進む「成熟期」にこんな大袈裟な都市計画を本気で試みる人もいないし、それを可能とする土地も、もはや地球上には残されていない。
もう少し現実的な処方箋として「再開発型」がある。既存の都市の一部分をごっそりと立て直すのがこの方法である。単体の建築の立て直しではなくて集団的、連続体として変えていくので、広場の施設だったり、道路の引き直しも可能であり、大胆に荒業を使って変更できるのだ。1939年にニューヨークでコロンビア大学の所有地に完成した十四のビルからなるロックフェラーセンターがこのタイプでは世界初といわれている。その後20世紀において世界の各都市でコピーが濫造されてきた。20世紀半ば以降の「成長」の時代にピッタリはまった処方箋だったのだ。都市が高密度化の圧力にさらされたとき、幾つかの敷地を統合して広場も緑地も文化施設もある理想的都市環境を作るということが狙いであった。日本では六本木ヒルズや梅田のグランフロントなどが事例として上げられる。
もっと地味な処方箋としては、「規制型」が上げられる。これは特定の地域、地区にある規制を定めることで、このルールにより統一された都市景観を作っていこうとするものである。実際には既存建築物が建て替わるときに、この規制を適用して建築デザインを実現していくもので、恐ろしく気の長い都市計画だともいえる。こんな気の長い方法ではグローバルな都市間競争に勝てないと否定する人と、そもそも都市とは時間をじっくり掛けて整備していくものだという肯定派に分かれるが。実際は20世紀初頭以降、世界のほとんどの都市にこの「規制型」の都市計画の網がかけられることになった。行政当局にとってはそれしか選択肢がなく、結局20世紀の都市における権力と市民との関係を成り立たせる現実となった。外壁はレンガにすることなど、材料から色まで厳しく規制が適用されているヨーロッパの都市から、高さや容積率だけを定める緩いルールで規制する都市まで現在規制の無い事由放任の都市は地球上にはほとんど存在しない。日本においても例外ではないが、にもかかわらず、そこに住む人々が満足できるレベルかというと、ほど遠いのが現状である。

なぜ「規制型」の都市計画は人々の満足を得られないのか
規制という方法で魅力的な都市や街が形成されるには二つの条件が必要である。
一つは、その都市を構成する建築デザイン(意匠)と素材の選択の幅が狭いことである。歴史を遡って、これらの選択の幅が狭い時代は、日本でも見事に統一感のある街並みが形成されてきた。しかし今日では建築デザインの選択の幅は、ほぼ無限であり行政がどんな規制を定めようとも、コスト抑制の為に規制を出し抜いたり、他の建物より少しでも目立つために規制の裏をかいたりする。設計者やデザイナーは規制を徹底して骨抜きにしていく。土地の細分化や行政の強制力が低下している現在において、これらの規制は無力に等しくなっている。
二つ目は時間である。都市がゆっくりとしか更新されない成熟した時代では、この手法はほとんど実効性を持たない。100年経過してもやっと数軒のビルしか立て替えられない状況では、住む人々が規制に対してポジティブな情熱を持つとは考えにくい。高度成長期では更新のテンポが速く、まだ規制が有効であったという見方もあるが、現実の日本の高度成長期における地主や建築主は自分の商売のことが優先され、都市全体の魅力創出といった価値の醸成に無関心な人が多かったのだ。さらに日本は以上のような一般論に加えて、独特な理由を持っている。先に述べたがパリ、ロンドンをはじめとする世界の優れた都市景観を有する都市は19世紀までの「成長」の時代を経験し都市の骨格を形成していた。
19世紀と20世紀以降では建築意匠(デザイン)の環境は一変する。この境界線は1940年の大恐慌前後のニューヨークまで引っ張ってくることが可能だ。エンパイヤステートビルやクライスラービルが建設された時である。この時点に間に合った都市は、都市の骨格を形成できたと言え、日本は遅れてしまったのだ。19世紀の建築は「建築様式」(ルネッサンス様式、バロック様式、テューダー様式など)によってコントロールされていた。この様式は時代と共に移り変わるが、おおむね一時代一様式でコントロールされていた。20世紀になり、この様式によるコントロール機能はモダニズムの台頭によって失効し、その後建てられる建築はアンコントロールの時代に突入しポストモダンを経て混乱していく。とりわけ欧米の後を追う日本は都市の骨格を形成できないまま、その後の都市を建設しなければならなかった。日本の都市は二重の困難が課せられていく、遅れてきた近代という歴史的与件と可燃の木造都市を不燃都市に作り替えなければならないという物理的与件である。

二重の困難を抱えた20世紀の日本人は海外旅行とテーマパークに惹きつけられていく。海外に行けば様式的にコントロールされた連続体としての都市景観に出会うことができる。もしそれを近隣で体験したければ入場料を払って入るゲートの中の虚構の街、すなわちテーマパークで体験できる。そこで人々はマーケティングのプロトコルが選択したテーマに従って、自動的に生成された「魅力ある都市」に身を浸すことができる。同じような構図は大型のショッピングモールにも読み取れる。特にアメリカはデモクラシーの国であり、資本には全ての経済行為が許され、アメリカの都市は「連続体」からモノとしての「粒子」へと徹底的に変質させられた。これは自由・平等という近代社会の原理が内包する矛盾を都市という空間で顕著な形として露呈したといえる。
日本はこのアメリカを後追いしてきたのだ。
ニューヨークは1910年代にこの都市の危機に気付き、「高さ制限」「斜線制限」「容積制限」など良好な都市環境を確保するための規制を実現させた。1916年に世界で初めて施行されたゾーニング(建物の携帯と用途を規制すること)に関する法律である。ニューヨークはその都市の形成が時代の境界線上に位置していたので、19世紀的建築様式による統制はまだ残存させることができたが、その他のアメリカにおける都市は20世紀の混乱と空虚の中で都市の骨格を形成せざるをえなかった。この時点でアメリカは「テーマパーク」という虚構の街を発明したのだ。1955年にアメリカの都市の中でも最も「粒子化」の進展したロサンゼルスに登場したディズニーランドであるのも、偶然ではない。
粒子化する都市の背後にあるモノ
20世紀の都市は、粒子化されモノ化して魅力を欠いた現実の都市があり、その外部にはテーマパーク化した、フェィクな連続体がある。これは新しい不毛な分断ともいえる。この都市の外部、周縁にある「テーマパーク」による華やかな視覚体験は、一時の慰めにはなるが、現実の都市の救いにはならなかった。ここで資本が考えることは、現実の都市もまたテーマパークの手法で武装すればいいという思考である。福岡市のキャナルシティ博多、カレッタ汐留、六本木ヒルズなどは現実の都市のコピーであったはずのテーマパークを、いつの間にか現実の都市がコピーし始めている事例である。この新しく出現した都市再開発による巨大な塊、ビッグネスは当然環境にも大きなダメージを与える。巨大な敷地を買収するための膨大なコスト、環境負荷の保証に投入される資金、その開発コスト回収のために行政へは規制緩和を求めプロジェクト全体の規模は、累乗的に肥大していく。
悪夢のような循環である。この都市におけるビッグネスは資金調達のテクノロジーを1980年代以降飛躍的に発展させていった。都市開発の巨大化は資金調達テクノロジーの進化そのものだったのだ。この悪夢から逃れるには、社会の上から下へというベクトルではなく、下から上へというベクトルの可能性を探ることが有効であると思う。この規制型都市再開発の最大の欠陥は、都市に対する具体的でポジティブなヴィジョンを描けないことである。描かないかもしれないが、規制はできても夢は描かない。この規制自体も資本に出し抜かれ、いかに金を儲けるかという不毛のゲームが都市に展開している。
結びとして
先に述べたように、19世紀以降の近代産業社会における文化領域を推進してきた原動力は広義のモダニズムに他ならない。ポスト産業社会がその前身である産業社会の批判となり、文化の質的変換を迫った。この時点でポストモダニズムが現れたが、ポストモダニズムも文化を支え、表出すべきものの不在によって、単なる消費社会におけるイメージの個性化、差異化によって自らを消費し尽してしまう運命にあった。と佐伯啓思氏は指摘する。20世紀は大衆社会とモダニズムは退屈な、均質的な都市空間を形成してきた。しかし建築には消費し尽しえない領域が存在する。それが空間、都市というものではないだろうか。社会と都市の生きる意志の反映としての空間は、消費され尽くされない強さと高貴さを有しているという事実は厳然と存在している。
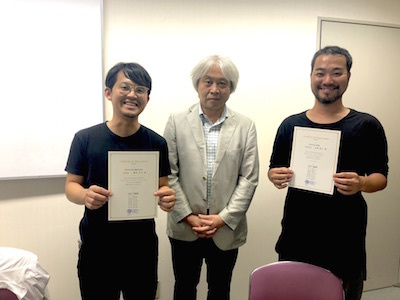
「リアリティ」が都市形成の目標となる計画である。その場所に暮らす住民自身の「リアリティ」が主役となるべきである。まず住民を尊重し、その街が受け継いできた私的な記憶を学ぶこと。これからの川端組。はこれまで18年間積み上げてきた不動産業からは離れていくことだろう。「一周遅れてそこに在る街」をモチーフにしたKawabata-channelを広げていく。場所、空間を育てていきながら、意識を共有できる人達を醸成できるフラットな空間を立ち上げていく。不動産の紹介も強度を持って絞った内容で紹介し本当に意識を共有できる人と出会っていく。5年後、10年後に互いに価値を分かち合うために。しかしあくまでもオーナーの資産を預かる訳なので、これがオーナーの資産の価値の最大化であるという信念がある。物件の輪郭を縁取るように紹介していく、「そこには住む人が幸せにならなければ売り手も幸せにならないという強い思いが込められている。だから川端組。のリノベーションは遠い処からソートされる。それは今までの不動産業が決して見なかった、見えなかった領域である。
川端氏は昨年5月「イマジン」を自費出版した。
私たちの世代(1950年代生まれ)にとって、ジョン・レノンの「イマジン」のビデオ・クリップでオノ・ヨーコが見せるパフォーマンスは印象的だった。窓という窓が閉ざされた暗い部屋で白いピアノに向かって歌うジョン。床に座っていたヨーコは立ち上がり窓を次々に開けていく。こうして部屋は少しずつ明るくなっていく。心在る人に今も歌い継がれているこの「イマジン」はヨーコも「グレープ・フルーツ」という本にインスパイアされたものだと、ジョン自身が語っている。ヨーコがジョンに与えた世界を変えるためのキーワードだった。
地下水の流れる音を聴きなさい。
心臓のビートを聴きなさい。
地球の回る音を聴きなさい。
想像しなさい。
千の太陽が
いっぺんに空にあるところを。
一時間かがやかせなさい。
それから少しずつ太陽たちを
空へ溶けこませなさい。
ツナ・サンドウィッチをひとつ作り
食べなさい。
石を空に投げなさい。
戻ってこないくらい高く。
呼吸しなさい。
グレープフルーツ・ジュース(1970年)
オノ・ヨーコ 南風 椎訳 より。
はじめに
9月になっても暑さが続く中、関東千葉では台風15号の上陸で停電が続いているエリアがある。この台風による暴風雨、とくに風による被害は予測を超えているようだ。このような状況にもかかわらず、今回は千葉県に在住されているパワープレイス社長前田氏に登壇いただいた。
前田氏は私の記憶によると鹿児島県の出身で、明治大学OBである。1981年に内田洋行入社、1997年エンジニアリングセンター長、2002年事業法人営業部部長、2006年九州支店・支店長、2010年執行役員オフィス環境本部事業部長を経て、2013年よりパワープレイス株式会社副社長、2017年同社代表取締役社長を務めている。
エンジニアリングセンターは前田氏が新規で立ち上げ、事業法人営業部と九州支店では市場活動を推進し、マーケットを拡大してきた。パワープレイス(株)は内田洋行グループで、ファシリティマネジメント、空間デザイン、ICTソリューションを事業内容として、17年前に内田洋行のデザイン部門が独立して出発した。エンパワーメントをテーマとしてパワーが溢れる空間を提案し続けている。前田氏は設立7年後から社長に就任され現在に至っている。

今月のテーマは「繋がるデザイン」街・人・チームを元気にするリレーションデザインである。ここに集まるデザイナーを前田氏は「拘る 変態デザイナー」と呼ぶ、今回の話はその変態デザイナー達の物語である。パワープレイスはチームが共感する場を多く設けている、チームの発表会も全員参加型で新人は運営でデビューし、共感できる時間を体験しながらそのノリの中でチームの空気に感染していく。ノリが大事だと前田氏は言う、そこにはリレーションという考え方が在りチームの視点として固定され、空間が意味を成し、モノが物語となり社会と繋がっていく。これがパワープレイスのデザインであり、方法である。繋がりが次の繋がりを生み、街やチームや人、そして自分自身が楽しみ元気になっていく。
特に林業における国産材を活用して地域が元気になる活動の輪「日本全国スギダラケ倶楽部」は注目される。
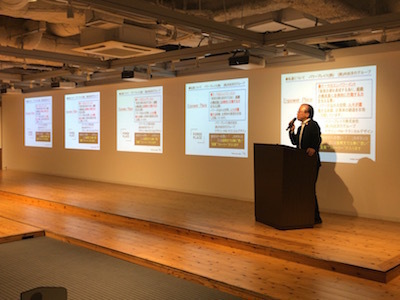
エンパワーについて
今月のテーマ、リレーションデザインを実現するために、パワープレイスは5つのコトを実践している。「POWER」の実践である。この言葉を紐解いてみる、
P(Professional)専門集団としての活動
O(Originality)豊かな創造性による価値ある場の実現
W(Work Place)「働く」「学ぶ」「集う」場の構築
E(Engineering)トータルエンジニアリングでファシリティ構築と運用を推進
R(Relation)リレーションデザイン
で「エンパワー」を実現する。
ここで今回のテーマで最も関係あるエンパワーについて述べておきたい。
エンパワーは能力開化や権限付与ということで、個人もしくは集団が自らの生活への統御感を獲得し、組織や社会の構造に外殻的な影響を与えるようになることと定義される。この考え方は現在大きな広がりを見せていて、保健医療福祉、教育、企業などの分野で取り入れられていて、そこに関わる人々に夢や希望を与え、勇気づけ、人間が本来持っている生きる力を湧き出させる、湧活という広義の働きを持っている。エンパワーメントはもともと20世紀を代表するブラジルの教育思想家パウロ・フレイルの提唱により社会学的な意味で用いられるようになり、ラテンアメリカを始めとした世界の先住民運動や女性運動さらには広義の市民運動などの場面で実践されるようになった。エンパワーメントの概念における焦点は人間の潜在能力の発揮を可能とし、平等で公平な社会を実現することである。
単に個人や集団の自立を促すだけではないのだ。この概念の基礎を築いた人はジョン・フリードマン〈カリフォルニア大学(UCLA)名誉教授・ブリティッシュコロンビア大学(UBC)名誉教授。世界各国の都市、地域開発の関わる実務家や研究者に、理論と実践の両面で、大きな影響を及ぼしてきたプランニングの巨匠。近年はエンパワーメント、市民社会、世界都市などをめぐる論考で先進国及び途上国の都市・地域開発に新たな視座を開く。〉でエンパワーメントを育む資源として、生活空間、余暇時間、知識と技能、適切な情報、社会組織、社会ネットワーク、労働と生計を立てるための手段、資金、を挙げている。それぞれの要素は相互依存関係にあり、地方自治や弱者の地位向上など下から上へのボトムアップしていく課題克服する中で育まれ、活動のネットワークを生み出し、信頼、自信、責任などの資本を育てていく、これがエンパワーメントの鍵である。

「場所」の力について
パワープレイスがエネルギーに満ち溢れた活動を展開するのは「場所」である。「場所」には力がある。この場所の力を喚起するものは沢山ある、人間の記憶に働きかける身近にあるささいなモノであったり、環境に関わる温度や湿度や風であったり、建築やインテリアを構成する素材とそれを構成する色彩や調度、いわゆる意匠と呼ぶものである。それらはその場所に関与する人間の受容する力に大きく左右されて「場所」として立ち現れる。どんな記憶(歴史と言ってもよい)を持って、どこに座って、どんな会話を交わすのかによって「場所」はゆらぎ、変化していく。このように「場所」は人間に大きな力を及ぼし、人間もまた「場所」に大きな環境的インパクトを与えているといえる。
私の専門のスペースデザインについて触れてみたい。「デザインとは、見えない力を、見える形にすること」とするならば、「場所」をデザインすることは、人間が潜在的に持っている力をデザインすることに繋がっていく。地表を真っすぐに歩いていくと、もとの地点に戻るはずである。地球は丸く面として閉じているからである。また地表には凹凸があり様々な地形として表れている。人間は農耕を始めて以来、開墾や灌漑で、そして現在に至るまでの都市化でその地表という「場所」に大きな影響を与え続けてきた。また地表に凹凸があるように、空間にも歪みがある。一般相対性理論では、重力は時空の歪みのことである。重力が大きい場所は、空間が大きく歪んでいる場所といえる。この重力の濃い場所が物質であり、電子も太陽も人間も濃厚な「場所」なのだ。DNAが生物の形を決めると言われるが、レシピや設計図だけで料理や機械や建築が再現できないように、そこには職人やシェフや建築家が不可欠のように、<建築こそ唯一技術の進歩とは相関することのない表現領域なのではー坂茂>同じDNAで全く同じ生物が成長するとは限らない。ほとんど全てがクローンである桜の品種、染井吉野でさえ、一本一本の個性や赴きが異なる。それを決めるのは気候や土壌、周辺の植生や環境である。
つまり「場所」の力に他ならない。近代が建築や都市で展開して実現させてきた、隅から隅まで均質である意味開放的で無駄のない、闇のない「場所」は、ともすると退屈な場所となってしまっている。便利になりすぎることが、不便に感じる逆説に転じているとも思われる。かつての日本空間は、踏んではいけない畳の縁や茶室の躙り口、神社の結界、さらには開かずの間など、それが在ることで場所に奥行きや物語を与えてきた。そして力をも与えてきたのだ。
「悪所」にこそ力があったのだ。

「場所」の力を生み出す「空」と「間」
日本人は漢字の「空」に、「うつ」や「から」などの音を当てた。「うつ」は「空」であると同時に「全」であり、空っぽだからこそ、そこにエネルギーを込めて充実させることができる。
「うつ」からは「うつつ」という言葉が生まれる。うつ=現であり、現実はうつろいゆくものであり、うつろな空間、うつろな時間から日本の場所は捉えどころがなく多様でダイナミックに動くものである。「うつ」から時の変化を意味する「うつろい」が派生したように日本の場所は時間と空間が混然となって未分化である。ここで「間」が重要な概念として浮上する。また「から」は「空」であり「殻」のことである。そこに「ち」、すなわち魂が宿ると「ちから」になる。人が火事場のバカ力のように、完全な力を発揮することはめったにないが、この「ちから」を引き出す場の代表が、相撲の土俵である。天円地方の古代中国の宇宙観(天は丸く、地は方形)や赤房、青房などの陰陽五行のシンボルによって力士の気力と体力が横溢する十五日間の「場所」を出現させる。
また大乗仏教によると「空」の原語はシューニャ、もともとは「からっぽ」という意味である。中が空っぽなまま風船のように「膨れる」という意味を持っている。「空」と「無」の違いはどうかというと、「無」は「何かが無い」ことを意味し、「空」は「有るべきものが無い」もしくは「有るはずのものが無い」ことを意味する。さらに中身だけではなく、容器そのものが有るのか無いのか、はっきりしない場合も「空」という言葉が使われる。人はみな、この世の神羅万象は確実に有って、中身もしっかり入っていると信じてやまない。これが迷いの根源であるとブッダは見抜いたのだ。
そしてこの世のそういう在り方を、大乗仏教は「空」という言葉で表現した。「空」には様々な面が秘められている。その中で最も大切な性質は無限のエネルギーである。人はともすると中身が入っているほどエネルギーが高いと考えがちだが、満員電車のように中身が入っているほど固着して身動きが取れなくなる。中身が少ないほどエネルギーは自由自在に活動できる。すなわち「空」であってこそエネルギーは最高度に活動できるわけだ。「空」はベクトルを持たないエネルギーが充満して状態なのだ。
「間」という概念に戻る。明治大学の神代雄一郎氏の建築意匠論によると、九間(ココノマ)が全盛を極めた時代があったという事実を指摘している。足利義政の東山殿にあった会所の主座敷、嵯峨之間がその代表としてあげられている。会所とは、ミーティングのために特別に設けられた座敷で、室町時代に連歌会や茶寄合など寄合性を特徴とする文芸や芸術と密接に関わりながら本格的に日本建築の中にあらわれた。足利義教の室町殿の寝殿にも仁和寺にも九間があり、中世の住宅の中の寝殿、会所には傑作が多い。主座敷の典型としての三間四方の正方形という形式が持つ中新世・四方性は能舞台や鞠懸(マリガカリ)、さらには城郭の天主や軍船にまで現れている。神代氏がもっとも好きな日本の部屋は二畳上段わきに付け書院のある残月亭であり、飛雲閣の柳の間である。
「昔の人たちが六間(十二帖)に感じた空間意識と現在の日本人が六帖に持つ空間意識はほぼ同じ、九間(十八帖)の空間意識と十帖の空間意識もほぼ同じ」時代とともに何時しか日本人の空間意識は半分に切り詰められたのだ。神代氏はこの切り下げに抵抗し「間」の復活を主張してきた。神代氏の九間論は史的考証ではなく、現代にも応用がきく意匠論であった。その論の射程ははるか古代の農耕集落の中核における、柱と柱の間から派生した「間」という感覚、観念そして無意識の生成の始原へと向かう創造力であったのだ。

むすびとして
パワープレイスは「場所」を動かすスイッチとして、
かたる(物語を生み出す場所を醸成する)
もてなす(金銭沙汰ではなく相手の為に手間暇かける)
ひろげる(違いを認め、違いを理解し多様性を知る)
あそぶ(自由であることは夢中になれること)
のる(状況に応じて醸成されるグルーブ感とドライブ感)
まなぶ(学習は「まねび」、物真似から始まる)
つくる(「協創」は発送を自由にし、共有・共鳴する)
の7つをあげている。そして、このスイッチを押すのは人である。
今回の最後に、個人と集団の精神構造について触れておきたい。個人にはすでに矛盾があり、超自我、自我、エズに分けられる。超自我からの命令―これは道徳的規範ということになっていて、簡単に言えば善悪である、そして自我は損得で、エスというのは快不快である。端折って単純化して言えばこうなる。だから善悪と、快不快というのはしばしば矛盾する。これは悪であるけれど快感であるとか、快感であるけど損であるとか、だから個人というのはこれらの葛藤や矛盾を常に抱え込んでいる。そういう葛藤の構造が社会の中でも葛藤の行動と同じになるわけだ。
ここで抑圧というものの起源を考えると、初めは自己抑圧で、人間が自分の欲望を抑圧するのは、他から禁止されたり押し付けられたりするからではなく自己抑圧である。人間は本質的に自ら自分の欲望を抑圧し自分を正当化する存在である。人間は自分の欲望を全て満足させることができない、だから自分で自分の欲望を抑圧する、「自分はそれをしてもいいんだ」というジャスティフィケーションとして、他の権威を持ってくるに過ぎない。そうすることによって、自分の無力と直面せずに済み、自尊心を守っているわけである。自分が現実とずれているとか、欲望に対する限度がないことを知らないということに、加えて人間の欲望は相矛盾している。
一つの欲望を満足させることが他の欲望を挫折させることになる。だからそういう欲望を整理する規範というものが必要となってくるわけで、その規範のために外的権威を必要とする。だから権力というのは自己疎外で、抑圧的な権力と見えるものは、人間の自己抑圧の外在化なのだ。抑圧的な権力を、人間の内なるものが支えている。これを自覚すれば、そこに在る自己疎外を克服する可能性が生まれてくるのではないかと思う。

社会というのはどうやって変わっていくのか、集団の精神構造と、個人の精神構造は同じなのだ。個人というのはそれぞれに歴史を背負った存在で、集団にも歴史があり、同じく歴史を背負った存在なわけである。集団というものは共同幻想で支えられていて、ここでいう共同幻想は集団を構成している各々の個人の持つ私的幻想を共同化したものである。個人の持つ私的幻想には共同化された部分と共同化されていない部分がある。共同幻想というのは集団を構成するメンバー全員の私的幻想の一部分でしかなくて、あくまで一部分の共同化でしかないわけで、共同化されないで私的な幻想にとどまっている部分のほうがはるかに多いわけだ。どのような集団に属していようと個人は社会と自分との間にどうしてもしっくり行かない、場違いな感じがある。共同幻想というのは、一旦成立すれば固定化し、硬直化し、私的幻想を吸い上げていく機能がだんだん弱まっていく。
だから既成の集団に対して人間は常に不満であるが、この共同化されないで私的なものにとどまっている幻想も常に表現を求めるので既成の集団の中で共同化されない私的な幻想は、それが共同化できるような集団を作ろうとする力になるわけだ。そういう力で社会は変わっていくのでは・・・あるいは社会がまるごと変わらなくても、少数の私的幻想を吸い上げるサブカルチャーのようなものが沢山出てきてもいい時代になったと思う。
今月もいい「気づき」を頂きました。

