はじめに、川端組長と頼りになる添え木の榊原氏のこと。
2019年10月定例会講師は京都一ファンキーな不動産屋を自称する1977年生まれの株式会社川端組。代表取締役組長 川端寛之氏である。
川端組長は2000年に大学を卒業後、技術専門学校で宅地建物取引士の資格を取得し、その後自由な職場環境に恵まれて不動産業の経験を重ねた後、2014年に起業している。取り扱う物件のユニークなリノベーションを企画提案しながら、感度の高い人やマイノリティの人にも選択肢の幅を広げながら日夜奮闘している。そのリノベーションはシンプルでユニークである。輸送用コンテナや建設現場に使われる単管足場などを、普通は建築設計には取り入れられないデザイン要素を大胆に企画し実現していく。それらはニッチな要望に突き刺さり、余白とブラックな部分に満ち満ちて、建築と街づくりの可能性を広げているように思う。店舗付き住宅が慢性的に不足する中で既存の街を活性化させるために「あきらめたくない、あきらめない。」不動産物件を生み出している。2018年1月より南吹田ファンキーステーションを立ち上げて南吹田琥珀街の街づくりを手掛けている。
今回の定例会は初めての試みとして、榊原允大氏が聞き手に加わっていただき進行した。榊原氏は1984年愛知県生まれで、2007年に神戸大学文学部を卒業している。芸術学部の研修では建築を選択し、2008年に建築リサーチ組織RADを立ち上げて活動を開始している。プロモーションディレクターとして地域の街づくりNPOなどを手助けしている。リサーチの新解釈を提案し、周辺、地域との関わりを重視したユニークなプロジェクトを複数進行させている。2016年から愛知県岡崎市で「おとがわプロジェクト」、兵庫県明石市では明石市立図書館の「ほんのまち明石」の取り組みなどワークショップキットなどを提案しながら進めている。いずれ機会があれば是非聞いてみたい話である。

南吹田琥珀街にもどる。
ことの始まりは2018年に南吹田駅が開業するにあたって、2016年より周辺街区の開発に向けて、設計を担当していた角直弘氏が川端氏に設計図面を見せたことから始まる。多くの開発は最低限の都市計画規制に準拠した上で、住民や近隣の意見をあまり入れずに進めてしまう。南吹田も同じ状況であったが、川端氏がこの業界の定められた流れに異を唱えた。そこで角氏がこれを聞き入れて、企画に川端氏が参加することから始まる。「街をこうしたい、こういう人に来てもらいたい」が描かれないうちに設計図が出来上がっていることへの違和感を川端氏は感じたわけである。成熟社会を向かえても開発の波をかぶっていない街区は貴重で、そこには未来に残したい風景がある。日本の中でも沖縄のはまだその空間が色濃く残ると、川端氏は語る。
東京を代表とする日本の都市は、太平洋戦争直後の焼け野原から、復興期、開発期を経てやがてグローバルな資本、欲望、情報、権力の集中する拠点となり、半世紀を超える。このような時間の中で物的、社会的変化を続け、今日本は21世紀を迎え、成熟期と言われて久しい。これから、どのような都市計画が日本に必要なのか<もう少し規模を縮小して街づくりと言ってもいいが>、どう見ても魅力に欠ける日本の都市や街の景観をどうしていくのか、それを考えていくことが今回の中心テーマだと考える。

高度成長期から成熟期への転換は急激過ぎた転換であったため、今日の日本社会は混乱していると言える。年金や福祉問題、外国人の受け入れを含む人口問題、文化や芸能、<都市や街に伝承されてきた祭りや神事とそれが行われる場所はその多くが無くなっている。>に至るまで関連しながら都市をめぐり、深刻な混乱を引き起こしている。巨大開発やマンション開発、それをめぐる近隣とのトラブル、その調停手法の未熟さ、加えて都市景観の醜悪さも指摘されている。高度産業社会が産んだ<もの>の中にすでに建築も繰り込まれているのだ。このリスクに満ちた都市や街をどのように未来につないでいくのかが問題なのだ。ここで少し時間を巻き戻して、都市計画を考えてみたい。
街づくりの都市計画的処方箋とは
都市計画の処方箋はいくつかに分類される。オーバーオール型は巨大で派手な都市計画の極致である。1960年にブラジルの首都となった、オスカー・ニーマイヤーがデザインしたブラジリアの様に、野原の上に一から都市全体をデザインし実現するのが「オーバーオール型」都市計画だ。高度経済成長期には可能であった、日本では規模ははるかに小さいが郊外型ニュータウンがこの都市計画手法に当てはまる。しかし中国ですら近い将来、いやもうすでに人口の伸びが止まると予想され、世界スケールで進む「成熟期」にこんな大袈裟な都市計画を本気で試みる人もいないし、それを可能とする土地も、もはや地球上には残されていない。
もう少し現実的な処方箋として「再開発型」がある。既存の都市の一部分をごっそりと立て直すのがこの方法である。単体の建築の立て直しではなくて集団的、連続体として変えていくので、広場の施設だったり、道路の引き直しも可能であり、大胆に荒業を使って変更できるのだ。1939年にニューヨークでコロンビア大学の所有地に完成した十四のビルからなるロックフェラーセンターがこのタイプでは世界初といわれている。その後20世紀において世界の各都市でコピーが濫造されてきた。20世紀半ば以降の「成長」の時代にピッタリはまった処方箋だったのだ。都市が高密度化の圧力にさらされたとき、幾つかの敷地を統合して広場も緑地も文化施設もある理想的都市環境を作るということが狙いであった。日本では六本木ヒルズや梅田のグランフロントなどが事例として上げられる。
もっと地味な処方箋としては、「規制型」が上げられる。これは特定の地域、地区にある規制を定めることで、このルールにより統一された都市景観を作っていこうとするものである。実際には既存建築物が建て替わるときに、この規制を適用して建築デザインを実現していくもので、恐ろしく気の長い都市計画だともいえる。こんな気の長い方法ではグローバルな都市間競争に勝てないと否定する人と、そもそも都市とは時間をじっくり掛けて整備していくものだという肯定派に分かれるが。実際は20世紀初頭以降、世界のほとんどの都市にこの「規制型」の都市計画の網がかけられることになった。行政当局にとってはそれしか選択肢がなく、結局20世紀の都市における権力と市民との関係を成り立たせる現実となった。外壁はレンガにすることなど、材料から色まで厳しく規制が適用されているヨーロッパの都市から、高さや容積率だけを定める緩いルールで規制する都市まで現在規制の無い事由放任の都市は地球上にはほとんど存在しない。日本においても例外ではないが、にもかかわらず、そこに住む人々が満足できるレベルかというと、ほど遠いのが現状である。

なぜ「規制型」の都市計画は人々の満足を得られないのか
規制という方法で魅力的な都市や街が形成されるには二つの条件が必要である。
一つは、その都市を構成する建築デザイン(意匠)と素材の選択の幅が狭いことである。歴史を遡って、これらの選択の幅が狭い時代は、日本でも見事に統一感のある街並みが形成されてきた。しかし今日では建築デザインの選択の幅は、ほぼ無限であり行政がどんな規制を定めようとも、コスト抑制の為に規制を出し抜いたり、他の建物より少しでも目立つために規制の裏をかいたりする。設計者やデザイナーは規制を徹底して骨抜きにしていく。土地の細分化や行政の強制力が低下している現在において、これらの規制は無力に等しくなっている。
二つ目は時間である。都市がゆっくりとしか更新されない成熟した時代では、この手法はほとんど実効性を持たない。100年経過してもやっと数軒のビルしか立て替えられない状況では、住む人々が規制に対してポジティブな情熱を持つとは考えにくい。高度成長期では更新のテンポが速く、まだ規制が有効であったという見方もあるが、現実の日本の高度成長期における地主や建築主は自分の商売のことが優先され、都市全体の魅力創出といった価値の醸成に無関心な人が多かったのだ。さらに日本は以上のような一般論に加えて、独特な理由を持っている。先に述べたがパリ、ロンドンをはじめとする世界の優れた都市景観を有する都市は19世紀までの「成長」の時代を経験し都市の骨格を形成していた。
19世紀と20世紀以降では建築意匠(デザイン)の環境は一変する。この境界線は1940年の大恐慌前後のニューヨークまで引っ張ってくることが可能だ。エンパイヤステートビルやクライスラービルが建設された時である。この時点に間に合った都市は、都市の骨格を形成できたと言え、日本は遅れてしまったのだ。19世紀の建築は「建築様式」(ルネッサンス様式、バロック様式、テューダー様式など)によってコントロールされていた。この様式は時代と共に移り変わるが、おおむね一時代一様式でコントロールされていた。20世紀になり、この様式によるコントロール機能はモダニズムの台頭によって失効し、その後建てられる建築はアンコントロールの時代に突入しポストモダンを経て混乱していく。とりわけ欧米の後を追う日本は都市の骨格を形成できないまま、その後の都市を建設しなければならなかった。日本の都市は二重の困難が課せられていく、遅れてきた近代という歴史的与件と可燃の木造都市を不燃都市に作り替えなければならないという物理的与件である。

二重の困難を抱えた20世紀の日本人は海外旅行とテーマパークに惹きつけられていく。海外に行けば様式的にコントロールされた連続体としての都市景観に出会うことができる。もしそれを近隣で体験したければ入場料を払って入るゲートの中の虚構の街、すなわちテーマパークで体験できる。そこで人々はマーケティングのプロトコルが選択したテーマに従って、自動的に生成された「魅力ある都市」に身を浸すことができる。同じような構図は大型のショッピングモールにも読み取れる。特にアメリカはデモクラシーの国であり、資本には全ての経済行為が許され、アメリカの都市は「連続体」からモノとしての「粒子」へと徹底的に変質させられた。これは自由・平等という近代社会の原理が内包する矛盾を都市という空間で顕著な形として露呈したといえる。
日本はこのアメリカを後追いしてきたのだ。
ニューヨークは1910年代にこの都市の危機に気付き、「高さ制限」「斜線制限」「容積制限」など良好な都市環境を確保するための規制を実現させた。1916年に世界で初めて施行されたゾーニング(建物の携帯と用途を規制すること)に関する法律である。ニューヨークはその都市の形成が時代の境界線上に位置していたので、19世紀的建築様式による統制はまだ残存させることができたが、その他のアメリカにおける都市は20世紀の混乱と空虚の中で都市の骨格を形成せざるをえなかった。この時点でアメリカは「テーマパーク」という虚構の街を発明したのだ。1955年にアメリカの都市の中でも最も「粒子化」の進展したロサンゼルスに登場したディズニーランドであるのも、偶然ではない。
粒子化する都市の背後にあるモノ
20世紀の都市は、粒子化されモノ化して魅力を欠いた現実の都市があり、その外部にはテーマパーク化した、フェィクな連続体がある。これは新しい不毛な分断ともいえる。この都市の外部、周縁にある「テーマパーク」による華やかな視覚体験は、一時の慰めにはなるが、現実の都市の救いにはならなかった。ここで資本が考えることは、現実の都市もまたテーマパークの手法で武装すればいいという思考である。福岡市のキャナルシティ博多、カレッタ汐留、六本木ヒルズなどは現実の都市のコピーであったはずのテーマパークを、いつの間にか現実の都市がコピーし始めている事例である。この新しく出現した都市再開発による巨大な塊、ビッグネスは当然環境にも大きなダメージを与える。巨大な敷地を買収するための膨大なコスト、環境負荷の保証に投入される資金、その開発コスト回収のために行政へは規制緩和を求めプロジェクト全体の規模は、累乗的に肥大していく。
悪夢のような循環である。この都市におけるビッグネスは資金調達のテクノロジーを1980年代以降飛躍的に発展させていった。都市開発の巨大化は資金調達テクノロジーの進化そのものだったのだ。この悪夢から逃れるには、社会の上から下へというベクトルではなく、下から上へというベクトルの可能性を探ることが有効であると思う。この規制型都市再開発の最大の欠陥は、都市に対する具体的でポジティブなヴィジョンを描けないことである。描かないかもしれないが、規制はできても夢は描かない。この規制自体も資本に出し抜かれ、いかに金を儲けるかという不毛のゲームが都市に展開している。
結びとして
先に述べたように、19世紀以降の近代産業社会における文化領域を推進してきた原動力は広義のモダニズムに他ならない。ポスト産業社会がその前身である産業社会の批判となり、文化の質的変換を迫った。この時点でポストモダニズムが現れたが、ポストモダニズムも文化を支え、表出すべきものの不在によって、単なる消費社会におけるイメージの個性化、差異化によって自らを消費し尽してしまう運命にあった。と佐伯啓思氏は指摘する。20世紀は大衆社会とモダニズムは退屈な、均質的な都市空間を形成してきた。しかし建築には消費し尽しえない領域が存在する。それが空間、都市というものではないだろうか。社会と都市の生きる意志の反映としての空間は、消費され尽くされない強さと高貴さを有しているという事実は厳然と存在している。
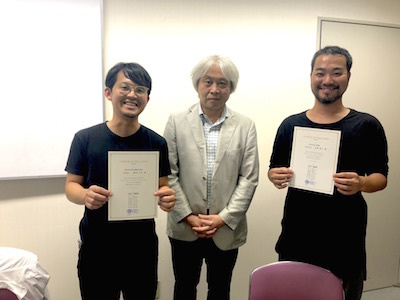
「リアリティ」が都市形成の目標となる計画である。その場所に暮らす住民自身の「リアリティ」が主役となるべきである。まず住民を尊重し、その街が受け継いできた私的な記憶を学ぶこと。これからの川端組。はこれまで18年間積み上げてきた不動産業からは離れていくことだろう。「一周遅れてそこに在る街」をモチーフにしたKawabata-channelを広げていく。場所、空間を育てていきながら、意識を共有できる人達を醸成できるフラットな空間を立ち上げていく。不動産の紹介も強度を持って絞った内容で紹介し本当に意識を共有できる人と出会っていく。5年後、10年後に互いに価値を分かち合うために。しかしあくまでもオーナーの資産を預かる訳なので、これがオーナーの資産の価値の最大化であるという信念がある。物件の輪郭を縁取るように紹介していく、「そこには住む人が幸せにならなければ売り手も幸せにならないという強い思いが込められている。だから川端組。のリノベーションは遠い処からソートされる。それは今までの不動産業が決して見なかった、見えなかった領域である。
川端氏は昨年5月「イマジン」を自費出版した。
私たちの世代(1950年代生まれ)にとって、ジョン・レノンの「イマジン」のビデオ・クリップでオノ・ヨーコが見せるパフォーマンスは印象的だった。窓という窓が閉ざされた暗い部屋で白いピアノに向かって歌うジョン。床に座っていたヨーコは立ち上がり窓を次々に開けていく。こうして部屋は少しずつ明るくなっていく。心在る人に今も歌い継がれているこの「イマジン」はヨーコも「グレープ・フルーツ」という本にインスパイアされたものだと、ジョン自身が語っている。ヨーコがジョンに与えた世界を変えるためのキーワードだった。
地下水の流れる音を聴きなさい。
心臓のビートを聴きなさい。
地球の回る音を聴きなさい。
想像しなさい。
千の太陽が
いっぺんに空にあるところを。
一時間かがやかせなさい。
それから少しずつ太陽たちを
空へ溶けこませなさい。
ツナ・サンドウィッチをひとつ作り
食べなさい。
石を空に投げなさい。
戻ってこないくらい高く。
呼吸しなさい。
グレープフルーツ・ジュース(1970年)
オノ・ヨーコ 南風 椎訳 より。


