底知れぬ食への願望を探究し続ける食の哲人である。その厚みのある体躯と柔和な表情の奥には豊富な食の知識が満々と湛えられ、時おり鋭い眼光を放つ。
門上武司氏は1921年に大阪外国語学校として設立され、2007年に大阪大学と統合された大阪外国語大学ロシア語学科に在籍した。
在学中より作詞家もず唱平氏が代表を務めるイベント企画会社「百十番舎企画」にてデパートや商業施設などの販売促進業務に従事し音楽・ファッションなどのイベントを手掛けそのアルバイトに明け暮れた結果、開設当初からの伝統あるロシア語学科を除籍となる。
当時知り合った人々である楠田恵理子、安井和美、松山猛、などとトークセッションのあと大阪の美味しい店で飲食を共にする中、食は人を繋ぎその繋がりを太くしていくことを学んでいく。
門上氏は幼少期から食べることへの探究心に目覚め、20歳代は中学時代の同級生で北新地の「いか里」店主と一緒にジャンルを問わずあまたの暖簾をくぐり続けた。
この時代に門上氏の原型が形成されていった。

30歳を過ぎた頃から関西のフランス料理店を食べ歩き、それでは飽き足らず毎年のようにフランスへの旅をするようになった。
そのフィールドワークによる食の経験と知識をもとに39歳でプロモーション会社を辞めて独立した。
その後、食を中心にした舞台で輝きを放ち「あの男ただ者ではない!」という噂が関西中に広まった。現在フードコラムニストにとどまらず編集者、コラムニスト、プロデューサー、コーディネーターというマルチな職域はこのようなキャリア形成から生み出されたものであり、関西にとどまらず日本の食シーンにおける最重要人物の一人となっている。
「食が元気にならないと関西の経済は元気にならない。」39歳から現在に至るまで年間1000軒以上、1日3軒の飲食店を訪ねる毎日である。
門上氏の「料理の世界」とは!
料理の世界の面白さは多角的なこと!人の心に働きかけ、刺激するものである。
例えばシズル感のある写真やビジュアル、映像は人をひきつける。
色彩は寒色よりも暖色の方が感覚に働きかける。それは生命を維持する大事なものであるが、それ以上のものを内包している。
人は外食に何を求めるのか?味わい、時間、空間、美味しいものを食べたいはもちろんだが、その日どういう味わいを求めるのか、その時間をどういう目的で過ごすのか、どういう居心地の空間を好むのか、生きるための食ではなくその次のニーズをいかに提供し叶えるのか、食は日常生活の中で目的を提供し続ける。
世界一の料理を食べること!から考えてみたい。
まずは「世界のベストレストラン50」はイギリスの雑誌が主催する料理界で卓越した才能を持つ人々を集めたユニークなコミュニティであり、世界の美食文化を讃えるものである。そのリストには、世界6大陸23カ国のレストランが含まれ、世界で最も優れた美食体験を表す指標となっている。
このリストはダイナーズクラブ「世界のベストレストラン50」アカデミーの投票に基づいて作成される。アカデミーはレストラン業界で影響力を持つ人々のグローバルリーダーで構成され、世界27の地域に分かれている。約1000人、各地域に委員長を含む36人が所属し、それぞれ7票の投票権を持っていて、7票の内少なくとも3票は所属地域以外のレストランに投じなければならない。
2002年に設立されて以来、2003年より継続して発表されている。
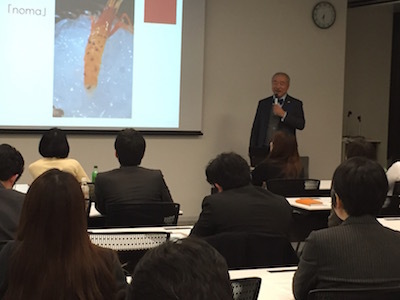
「Noma」
「世界のベストレストラン50」で1位を4回も獲得しているデンマークのレストランだ。
2015年1月から2月初旬までスタッフごと引っ越してきて東京のマンダリンオリエンタルホテルで期間限定レストランを開いた。
コペンハーゲンの本店では「ヨーグルトと蟻」の料理を出している。今回の「NomaTokyo」のメニューにもボタンエビに長野県産の蟻をまぶしたものが登場し話題となった。
価格は料理+ワイン・ペアリングで6万3千円、宿泊込だと151万4千円だが1か月2000席に対して、6万5千人の応募があった、うち70%は海外からの予約であった。
「Noma」を立ち上げたオーナーはレストランや高級デリの経営者でデンマーク飲食業界のカリスマ、クラウス・マイヤーそしてシェフはレネ・レゼビだ。
北欧はそもそもプロテスタントが多く美食とは遠い国であった。
「経済的には裕福な国でありながら、こんなひどいものを食べているアンバランスさに社会の目を向けさせなければならない」と考えたクラウス・マイヤーは事業の他にテレビ番組を持ち、国の機関にも働きかけた。
こうして彼は北欧のシューケースになるようなレストランー「Noma」プロジェクトに着手することとなった。
2004年に「新しい北欧料理のためのマニフェスト」を発表した。新しい北欧料理はその目的として「私達の地域を思い起こさせる、純粋さ、新鮮さ、道徳を表現すること。」「自給自足されてきたローカルな食材を高品質な地方産品に」あるいはサスティナブルであったり、「消費者、料理人、生産者、小売、研究者、政治家などが共同して北欧の利益を生み出す」など10か条が上げられる。「Noma」が用意できる年間2万席に100万人以上の予約がある。
「Noma」の成功はコペンハーゲンを訪れる人々の目的を変え結果、観光客は11%増加した。「Noma」はスカンジナビアの食材しか使わない!グローバリズムが進めば進むほどローカリズムは差異化を生む武器となる。
「NARISAWA」
かつて小田原市にあった港の前の小さなレストラン「La Npoule」、今だに語り継がれる伝説の店が現在の「NARISAWA」の起源である。
2011年シェフ成澤は「サスティナビリティとガストロノミーの融合」というテーマで自然保護に関わる料理を発表し始めた。
素材は全て日本のもの、素材を守る気持ちから生まれた世界初の「土のスープ」、「水のサラダ」、日本の森のエッセンス里山の風景が料理を通じて環境問題を訴え続ける。常に自然体であり、時の流れに身を任すように季節や風景を器の中に表現していく。
成澤由浩(1969年愛知県常滑市生まれ)ヨーロッパで8年間修行した後、個人の料理「InonovativeSATOYAMA Cuisine」というスタイルを南青山で確立した。
「いか里」
大阪北新地・本通の料亭「いか里」は1946年創業で三代目の稀代のくいしん坊の木村篤氏は門上氏の中学の同級生である、そんな彼が盛り付けた料理が会場で映された。食べ物の情報操作できる幅は大きい!750円の弁当も分解して再構成すると、6,000円もの料理に見えてしまう。私もしてやられました!分解と再構成による美的プレゼンテーションであり、価値の再構築である。
「富小路やま岸 」
京都懐石料理の料亭である。京都の伝統を守りながら、茶懐石のおもてなしの精神を基本に、四季の移り変わりを感じられる料理を提供。店主の山岸氏は「華道」「茶道」「書道」の通じそこで得た繊細な美しい感性を料理で表現する。季節の先取りと旬、名残りと走りが一皿で出会い表現される。寿司屋での修行経験を持つ店主は客の目の前でネタを料理する。最高のエンターティメントであるということである。これが楽しいからまた行きたい、人に喋りたい話のネタがることが大事、今の時代に山岸は質の高いネタを提供し続ける。まさに「出会いもの」という言葉を思い浮かべる。
白(tukumo)
奈良市三条町にある日本料理店である。「白」と書いて「つくも」と読む。「百」に一つ足らず、よって「つくも」である。店主の西原理人氏は「嵐山吉兆」で10年間修行を積んだ後、ニューヨークの「嘉日」精進料理で料理長、そののちロンドンの「UMU」でそれぞれ3年ほど働き、2015年より奥様の縁があり奈良で開店した。基調は日本料理で在るが時にはニューヨークやロンドンの色彩が増してアヴァンギャルドな献立となる月もある。鮮烈な黒文字の香り、先附の藤原宮跡の蓮池の水面、沢煮椀は黒い海苔が入った真っ黒な景色、肴は旬の魚の薄造りと金糸瓜など、これから奈良が面白い。

チェンチ
「岡崎」は琵琶湖疏水が流れる京都市の文教区である。長年イルギオットーネ本店のシェフを努めた坂本健氏は2014年2月にこの地に開店した。特筆すべきは店舗の空間デザインである。古い町屋を大胆にリノーヴェーションした。そのインテリアは外観からは想像できない。店名の「Cenci」とはイタリアのフィレンツエの方言で「古びた物、ボロ布」という意味である。入口を入ると「ほの暗い玄関ホールに降りる古い石造の階段があり、いきなりフィレンツエの路地に迷い込んだ感覚になる。ホールの左手には南禅寺に在る「ねじりまんぼ」という明治時代の遂道を模したレンガ壁の奥に4席のカウンター席が垣間見える。レンガは店舗改装の時半地下に掘り下げたときに出た土を、信楽の土と混ぜてスタッフが焼成したという凝りようである。正面の扉を開けると、そこは一階席だが左手のはるか眼下に広々とした半地下のダイニングホールが見下ろせ、シェフと4人のスタッフが働くオープンキッチンがその向こうの一階にある。どの席からも空間の一番奥にある坪庭が眺められる。お客様に来てもらうためにこだわりの店づくりをする。あくまでも料理は京都にこだわり京都料理を提供するがしめはパスタである。「Cenci」究極のローカリズムが交錯する食の空間である。
洋食おがた
長崎のホテルヨーロッパで柿本勝シェフの元10年間修行を積み、1998年には未来のグランシェフ全国料理コンクールでグランプリに輝いた緒方シェフ、「客の要望にできるだけ応えられる、割烹のような洋食店にしたい。」という思いで京都市中京区柳馬場押小路上ルに「洋食おがた」をオープンした。洋食好きをどう刺激し擽るのか。ハイレベルの接客と素材と味と空間にこだわった店である。河北農園の白菜マリネ、熊本の馬刺し、菜の花とホタルイカ、まながつおの焼霜、尾崎牛のビフカツ、ミンチカツのハンバーガ、3匙カレーなど・・・
まとめとして、
京都のムーブメントを中心に今回はチェーン店ではなく個店の紹介である。
生き残る、元気な外食産業とは、人に進めたくなるトリガーが埋め込まれ、人に伝えたくなるキーワードが物語を作る。
人を惹きつけるチャレンジとイノベーションを常に試み、コンセプトと目的が明確である。
ここでのローカリズムは差異化を産み出す大きな武器となる。地域で産する生産物は調理加工によって小さな価値から大きな価値に変わり経済効果を押し上げる力を持つ。
材料を分解し再構築する、科学的な知識に基づきそこに私達は何をしたいのか、表現したいのかという哲学を持ち続けることが大切なのでは。
文化的な戦争は目に見えない形でもうすでに次の段階に入ろうとしている。
「和食」がユネスコの無形文化遺産として登録された中、京都府立大学和食文化学科の活動にも注目していきたい。

むすびとして
18世紀のアダムスミスの時代までは「量」は問題となっていなかったが、「人口論」のマルサスの時代から「量」が問題となってきた。
そして、マルサスは量の市場が生まれる可能性があると予測した。私達は資本主義の欲望の対象として、量化されたモノを交換しあう社会を作ってしまった。
20世紀のビジネスモデルの前提は、19世紀半ばから急速に発達してきたマーケティングを基調にして、大量生産したプロダクトを店頭に並べ、匿名のお客様「顔の見えない人」がそれを買っていくということで推し進めてきた。
これは鉄道と電信が商圏を広げたことによって成立したモデルである。
大量生産した製品を広域で大量販売するモデルである。そうではなくて今、新しいモデルを探究する必要がある。今回の幾つかの事例は「顔の見える」ビジネスモデルでありその次を予測させる要素多く含んでいる。言わば「質」を問題としたモデルである。
フランスのポストモダン思想では、植物の根が生えるようなネットワークを「リゾーム」と呼ぶ。ネトワークというと、系統樹のように木の上の方に広がっていくという考えが主流だが、必ずしも上だけがネットワーク化されるわけではない。
地下茎の様に土壌でもネットワークは伸びる。それが「リゾーム」で、この「リゾーム」がニューロンネットワークのように伸びていき、その上にコミュニティやコモンズやソサエティができあがる。このネットワークのあちこちには「萃点」がある。
これは一種の複合ノードで、ハブは寄せ集めであるが、「萃点」はすべてそこから発して戻ってくる。様々な理が通過し、交差する点である。
<「萃点」とは和歌山県田辺市の偉人南方熊楠が唱える彼オリジナルの概念である。> 三月如月
本年度もご清聴ありがとうございました。


